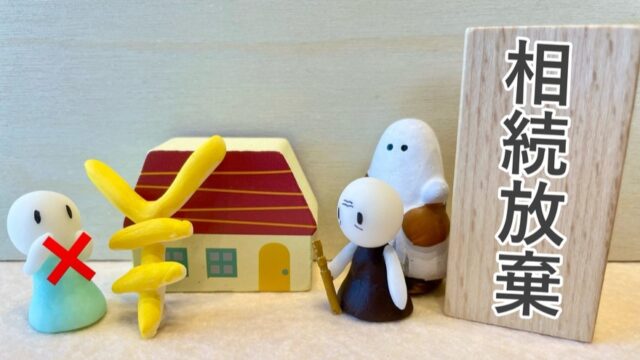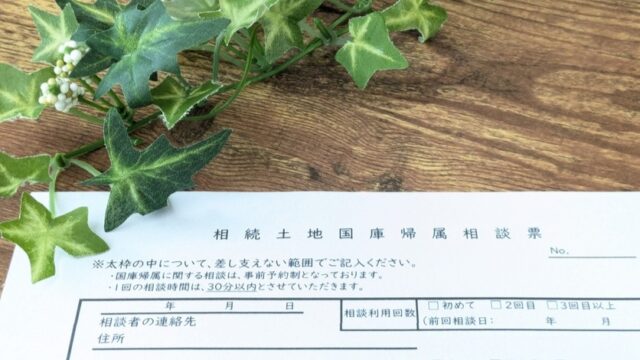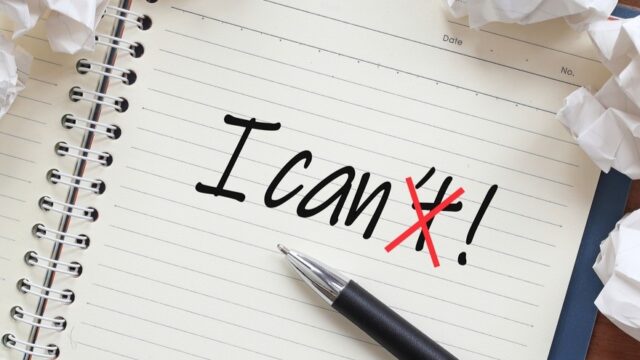相続税
相続税 1.6億円まで相続税はかからない? 相続税の配偶者控除の仕組みや要件、注意点をわかりやすく解説
「配偶者が相続すれば相続税はかからない」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実際に、相続税には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、配偶者が相続した財産については、最低でも1億6,000万円まで相続税がかからない仕組みになっています。この制度は非常に強力で、多くのケースで配偶者の相続税負担をゼロまたは大幅に軽減することができます。しかし、配偶者が多くの財産を相続すれば、一次相続では税負担が軽くなっても、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子どもたちの税負担が重くなる可能性があります。ほかにもいくつか注意点があり、「配偶者に相続させれば必ず得をする」とは限らないのです。今回は、相続税の配偶者控除の仕組みや適用要件、二次相続まで見据えた場合の注意点等をわかりやすく解説します。