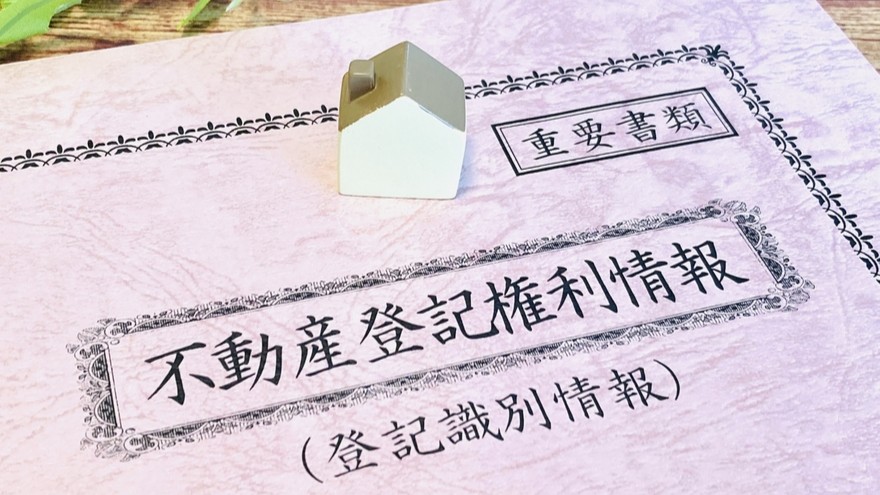相続によって土地や建物を取得したあと、登記(名義変更)をせずにそのまま放置している方は少なくありません。しかし、2024年(令和6年)4月から「相続登記の義務化」が始まり、登記を怠ると過料の対象となります。
これまで義務ではなかった相続登記がどうして義務化されたのか、疑問に思う方も多いでしょう。その最たる理由は、所有者不明土地・建物問題にあります。長年相続登記が放置されたことで、「誰の土地かわからない」「相続人が何十人にも増えて登記ができない」といった状態の土地や建物が増え、社会的な問題が発生していたのです。
この記事では、相続登記の義務化の概要やその背景、登記をしないままにした場合のリスク、さらに関連する新制度について、司法書士の立場からわかりやすく解説します。
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、新しい所有者の名義に変更する手続きです。
土地や建物といった不動産の権利状態は、法務局で、登記記録として管理されています。不動産の所有者が亡くなると、その不動産は相続人や受遺者といった新たな所有者のものになりますが、登記記録を変更するには新しい所有者が法務局で手続きをしなければなりません。このような手続きを相続登記といい、新たな所有者は、相続登記をすることで、その不動産が自分のものであることを第三者に証明できるようになるのです。
相続登記の義務化とは?
そんな相続登記ですが、2024年(令和6年)4月に施行された改正不動産登記法により、「相続または遺贈によって不動産を取得した人は、その不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」というルールが設けられ、一部で話題になりました。これを、「相続登記の義務化」といいます。
このルールには罰則もあり、正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった人は、10万円以下の過料の対象となります。
ここにいう正当な理由とは、たとえば次のような場合を指します。
- 遺産分割協議が調わないとき
- 相続人があまりに多数で、手続きに時間を要するとき
- 病気や貧困等の事情で登記ができないとき
このような事情があるときは期限を過ぎても直ちに罰則とはなりませんが、放置を続ければ法務局からの指導や過料の対象になるおそれがあります。
義務化によって、不動産を相続した人は、その権利状態を早期に明確化しなければならなくなったのです。
相続登記は「不動産を相続したことを知った日」から3年以内にしなければなりませんが、具体的にこの期限はいつから始まるのでしょうか。
最もわかりやすいのは、「相続人が一人で、特に遺言もない」ようなケースでしょう。この場合、被相続人が不動産を所有していたら、相続放棄をしない限りその相続人が新たな所有者となるので、3年の期間は、「被相続人が死亡した日」または「その不動産を被相続人が所有していたことを知った日」のどちらか遅い日から始まります。
次に「相続人が複数いて、遺産分割協議をする必要がある」ケースです。このケースがもっとも多いと思われますが、この場合、3年の期間はいつから始まるのでしょうか。
まず、遺産分割協議が終わらない間は、さきほどのケースと同様、「被相続人が死亡した日」または「その不動産を被相続人が所有していたことを知った日」のどちらか遅い日から始まります。そして、この状態では、相続登記の義務は相続人全員が負うことになります。その後遺産分割協議が終わって新たな所有者が確定すると、その遺産分割協議がまとまった日から3年が登記の期限となります。そして、この状態では、相続登記の義務は新たな所有者のみに課されるのです。
このように、相続登記の義務化における3年の期間は、「不動産を相続し、なおかつ、自分がその不動産の新たな所有者となった日」から始まります。被相続人が所有していたとは知らない不動産にまで過料が科されることはありません。
相続登記をしないとどうなる?
次に、相続登記をしないとどうなるのかを確認していきます。
相続登記をしないで不動産の名義を故人のままにしておくリスクは、以下のとおりです。
その1:不動産の売却や担保設定ができない
まず大きなデメリットとして、不動産を売ったり、不動産を担保にお金を借りたりといった取引行為ができないことが挙げられます。
不動産に関する取引をするときは、必ずその不動産の権利状態を示すための登記をします(売買であれば所有権移転登記・担保権の設定であれば抵当権設定登記等)。
この登記は、その取引をした現在の所有者が行わなければならず、亡くなっている名義人からすることはできません。つまり、相続登記をせずに不動産の名義を故人のままにしておくと、不動産に関する取引行為ができず、いざというときに不動産を売ったりローンを組んだりしてお金を工面することができなくなってしまうのです。
その2:相続登記の手続きが複雑化し、時間と費用がかかる
相続登記は、相続人全員の協力がないとできません(例外として、裁判手続きによる強制的な相続登記もありますが、かなり稀です)。この点、相続登記を10年、20年と放置し続けると、相続人が亡くなって次の相続が発生し、関係者がどんどんと増えていきます。
相続人が数十人に増えてしまった場合に、その全員に連絡を取って遺産分割協議書への署名や捺印をお願いする作業は、非常に労力がかかることが目に見えるでしょう。このような事態にならないためにも、相続した不動産はすぐに名義変更し、先の世代に手間をかけないようにしておきたいです。
その3:所有者としての権利を第三者に主張できない
次は法律上の権利に関するお話です。不動産を相続して名義を変えないでいると、本来の所有者であるはずの相続人が、その不動産についての権利を第三者に主張できなくなるリスクがあります。
相続登記をしていないと、不動産の所有権がどの相続人にあるのかわからず、第三者との間でトラブルになってしまうことがあるのです。不動産を適切に管理するためにも、早めに名義変更を済ませておきましょう。
その4:他の相続人と共同で不動産を管理しなければならない
不動産を含む相続財産は、遺産分割や名義変更といった相続手続きが終わるまでは、相続人が共有している状態にあります。
このような状態で不動産の管理(修繕やリフォーム、廃棄物の処理等)を行うとき、一部の行為は、相続人が1人ですることはできず、相続分の過半数をもつ相続人が協力して行わなければなりません。
このように、不動産に万一のことがあったとき、相続人間でスムーズに連携が取れないと管理行為ができなくなる恐れがあるので、名義変更を済ませ、管理者(=所有者)を明確にしておきましょう。
その5:過料を支払わなければならない
最後は、先ほども紹介した相続登記の義務化によるリスクです。2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化され、相続登記をせずに放置していると10万円以下の過料が科される可能性が生じました。
相続登記の義務化において、過料が科されるまでの流れは以下のとおりです。
- 法務局が相続登記されていない不動産を発見し、相続人に対して催告書を送る。
→ 法務局がこのような不動産を発見するのは、遺言書や遺産分割協議書など、他の不動産の登記で提出された書類にこの不動産が載っている場合や、あまりに古い時代の登記のまま放置されている場合などです。 - 催告書の期限内に相続登記がされない場合、法務局から裁判所に「相続登記義務に違反している人がいる」旨の通知がされる。
→ 先述のような正当な理由がある場合にはこの通知はされません。 - 裁判所が通知の内容を確認し、過料の額を決定する。
このように、相続登記の義務に違反していたとしても、直ちに過料が科されるわけではありません。法務局から催告書が届いた段階で、適切な対処をするようにしましょう。
相続登記が義務化された理由
このように、放置していると様々なデメリットがある相続登記ですが、なぜ義務化されることになったのでしょうか。
相続登記義務化の背景には、全国的に増え続ける所有者不明土地問題/所有者不明建物問題があります。所有者不明土地・建物とは、一度相続登記がされなかったために今の所有者がわからなくなった土地や建物のことです。なかには相続を繰り返して相続人が何十人にもなっているものもあり、管理や処分ができないため、困った近隣住民が行政に相談するようなケースもあります。
このような土地・建物は、公共事業や災害復旧の妨げになるほか、役所としても、固定資産税を徴収できずに困ってしまいます。
そんな所有者不明土地・建物問題を解決するために、相続登記の義務化が導入されたのです。これにより不動産の権利者が明確になり、国による管理がスムーズに行えるようになると期待されています。
所有者不明土地・建物問題が注目を浴びたのは、2011年に発生した東日本大震災のときでした。
災害復興のため、多くの事業者が建物の解体や土地の買収に取り組みましたが、その建物や土地の登記記録が古い情報のまま放置されており、所有者と連絡がとれない事態が多発したのです。その数は、全体のおよそ2割にのぼるといわれています。
所有者がわからない以上、無断で解体・売却することはできません。そのため、崩壊した危険な状態の建物が放置されたり、地域の再開発が進まなかったりといった事態が発生しました。
このように、災害が多い日本では、所有者不明土地・建物問題は災害からの復興を妨げる大きな要因となるのです。
相続登記の義務化に関連する制度
これまで相続登記の義務化について解説してきましたが、次は、相続登記の義務化にあわせてつくられた新しい制度について紹介します。
相続人申告登記
相続人申告登記とは、相続登記がすぐにできない場合に、法務局に「自分が相続人であること」を申告して、相続登記の義務を免れる制度です。
これは厳密には登記ではありませんが、ごく簡単な手続きで、相続登記の義務を免れることができる優れた制度です。遺産分割協議がまとまらない場合や相続人がたくさんいて登記が難しい場合に有効であり、「いつ過料が科されるかわからない」という不安を解消することができます。
この制度は、相続人であれば誰でも、1人で利用できます。他の相続人と協力する必要がないため、手続きの負担が少なくなっているのです。
(相続人申告登記について、詳細は後日の記事で解説予定です。)
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫制度制度とは、誰も引き継ぎたくないような土地を国に引き渡して、所有権を放棄できる制度です。
相続では、例えば遠方にある土地や山の中の土地など、管理負担が大きく、売ることもできないような土地を相続してしまうことが起こり得ます。このような場合に有効なのが、この相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度では、その土地が一定の要件を満たしていれば、相続した土地を国へ引き渡すことができます。ここにいう一定の要件とは、以下のような要件です。
- 建物が建っていない
- 担保権等、第三者の権利の対象ではない
- 通路として利用されていない
- 境界が明らかではない など
要件がかなり厳しく、おおむな10年分の管理費用相当の負担金も支払う必要があるため、利用を断念される方も多いですが、相続問題を解決する新たな選択肢として、今後の制度拡充が期待されています。
相続登記を放置しないために
最後に、相続登記を放置しないためにどのような対策がとれるかを簡単に紹介します。
まとめ
相続登記の義務化により、相続した不動産については、相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)をしなければならないと定められました。この義務に違反すると過料が科されるおそれもあり、国としても、所有者不明土地・建物問題の解決に力を入れている様子がうかがえます。
さらには相続登記を放置していると、過料を科されるだけではなく、不動産の管理・処分ができなくなったり、不動産の所有権を主張できなくなったりといった、様々なリスクも生じます。
相続登記を放置して手続きが複雑になってしまう前に、お近くの司法書士へご相談ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。