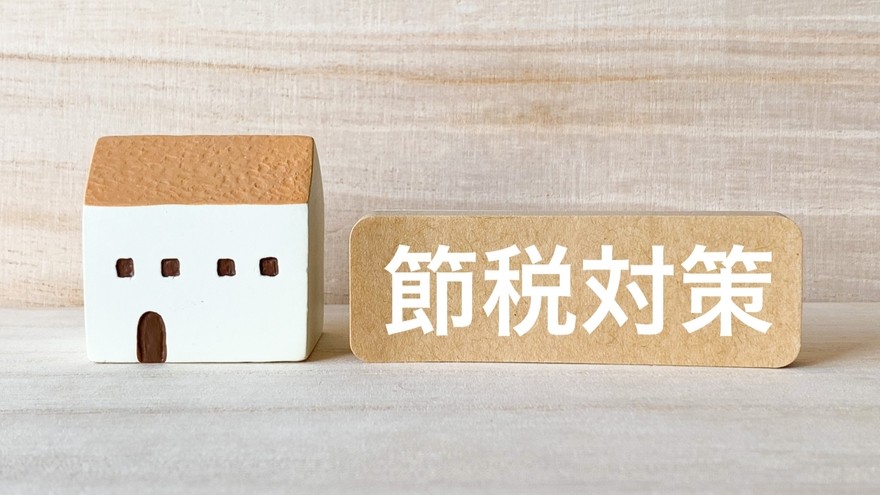親子間や夫婦間で財産の贈与をするとき、気になるのが贈与税でしょう。贈与税率は最高で55%にもなり、知らずに多額の税負担を負うケースも少なくありません。
一方で、税法では特定の要件を満たした贈与について、非課税となる特例制度が設けられています。こういった制度をうまく活用すれば、贈与税をかけずに財産を次の世代へ移すことも可能です。
この記事では、贈与税の基本と非課税となる6つの制度をわかりやすく解説します。
そもそも贈与税とは?
贈与税とは、個人(贈与者)から財産を受け取った人(受贈者)が負担する税金です。対象となる財産には現預金の他に株式や不動産も含まれます。なお、法人から財産を受け取った場合には、所得税がかかります。
贈与税は、1年単位(1月1日~12月31日)で考え、その年に受け取った贈与の合計額から基礎控除額110万円を引いた金額に対して課税されます。たとえば、1年間に500万円の贈与を受けた場合、500万円−110万円=390万円が課税対象となり、その金額に応じた税率(10〜55%)が適用されるのです。
なお、この110万円は贈与を受けた人(受贈者)ごとに計算されるため、例えば父と母から100万円ずつ贈与を受けた子どもは、100×2-110=90万円分の贈与について贈与税を納めることになります。
この基礎控除を活用した生前贈与の方法もあり、これを「暦年課税」といいます。
暦年課税の詳細や贈与税がかかる場合の計算方法はこちらの記事にまとめているので、あわせてご覧ください。
ただし、以下のような贈与には、贈与税は課されません。
つまり、「日常的な扶養義務の範囲内での財産のやり取り」や「社会通念上、贈与とはいいがたい物品のやり取り」は非課税とされています。
一方で、住宅購入や将来のための蓄えとして一括で資金を渡す場合は課税対象となるため、これから紹介するような特例制度の活用が重要です。
贈与税が非課税になる6つの制度
ここからは、代表的な贈与税が非課税になる6つの制度を紹介します。
いずれの制度にも条件があり、申告方法や期限にも違いがあるので、ご自身に合った制度をご検討ください。
その1:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(通称:おしどり贈与)とは、夫婦間で配偶者が居住するための不動産やその購入資金を贈与した場合に、最大で2,000万円+基礎控除110万円まで贈与税が非課税となる制度です。
詳しい要件は以下のとおりです。
(参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁)
一生に一度しか使えない制度ではありますが、長年連れ添った夫婦間で自宅を配偶者名義にしたい場合などにとても有効です。
なお、この制度の適用を受けるには、以下の書類を添付して、贈与税を申告する必要があります。
- 贈与の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄抄本
→ 夫婦関係を示すため - 贈与の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
→ 実際に住んでいる場所を示すため - 居住用不動産の登記事項証明書や居住用不動産の売買契約書など
→ 受贈者が確かに居住用不動産を取得したことを示すため - 居住用不動産の固定資産税評価証明書
この申告をしなければ2,000万円の控除を受けられず、贈与税の対象となりますので、必ず申告してください。
なお、この制度の注意点として、金銭ではなく不動産自体を贈与する場合は、不動産取得税(固定資産税評価額の約3%)や登録免許税(固定資産税評価額の約2%)がかかります。さらに贈与の登記を司法書士に依頼する場合、司法書士報酬も必要です。免除されるのは贈与税のみである点に注意してください。
贈与税は、贈与を受けた人(受贈者)が申告しなければなりません。
贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日(3月15日が土日祝日の場合、次の平日)までです。2月15日からは確定申告が始まる関係で税務署がとても込み合うので、贈与税の申告は、2月上旬のうちに済ませてしまうようにしましょう。
その2:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(住宅取得等資金の贈与)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(通称:住宅取得等資金の贈与)とは、父母や祖父母などの直系尊属から、居住用家屋の新築や購入、増改築等のために充てる金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合に、最大で500万円(省エネ等住宅の場合は1,000万円)+基礎控除110万円まで贈与税が非課税となる制度です。
詳しい要件は以下のとおりです。
さらに、新築等する家屋にもいくつか条件が決められています。
(参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁)
家を買うときに、「親に頭金を払ってもらう」「祖父母がお金をくれる」といったご家庭も多いでしょうが、この制度を使うことで、贈与税を軽減できます。
なお、この制度の適用を受けるには、以下の書類を添付して、贈与税を申告する必要があります。
- 受贈者の戸籍の謄抄本で、贈与者との関係を示すもの
→ 当事者の関係性や受贈者の生年月日を示すため - 受贈者の源泉徴収票や確定申告書の控え
→ 合計所得金額を示すため - 贈与の翌年の3月15日までに登記が完了している場合は、家屋(と土地)の登記事項証明書
- 新築に係る工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し等、契約の内容や取得の相手方がわかる書類
→ 登記事項証明書から判明する場合は添付不要 - その他、中古住宅である場合や省エネ等住宅である場合は、本制度の適用を受けるために必要な要件を満たしていることを示す書類
この申告をしなければ500万円または1,000万円の控除を受けられず、贈与税の対象となりますので、必ず申告してください。
その3:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(教育資金の一括贈与)
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(通称:教育資金の一括贈与)とは、父母や祖父母などの直系尊属から、教育のための資金を一括で贈与された場合に、最大で1,500万円(そのうち、学校等以外に支払う資金については500万円まで)+基礎控除110万円まで贈与税が非課税となる制度です。
※ 「一括贈与」という制度名ですが、枠内であれば複数回に分けて贈与しても問題ありません。
詳しい要件は以下のとおりです。
「教育のための資金」の要件は、以下のとおりです。
(参考:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁)
ただし、この制度は利用方法が少し複雑です。これまで紹介した制度は贈与税の申告時に追加資料が必要となるだけでしたが、教育資金の一括贈与では、贈与の時点で特殊な手続きが必要となります。
その手続きの流れは、以下のとおりです。
- 贈与者と受贈者の間で贈与契約を締結し、贈与契約書を作成する。
→ 贈与契約書には、当事者双方の住所氏名・贈与する金額、贈与の予定日を記載し、当事者が署名押印します。なお、受贈者が未成年である場合は、法定代理人(親)が代わりに契約します。 - 金融機関で、受贈者名義の「教育資金口座」を開設する。
→ 口座開設時には、①で作成した贈与契約書のほか、戸籍謄本等が必要です。詳しくは、各金融機関の案内を参照してください。 - 口座開設した金融機関に、「教育資金非課税申告書」を提出する。
→ 税務署への提出は不要 - 教育資金口座に、教育資金を預け入れる。
- 受贈者は、学校等へ教育資金を支払ったときに受け取った領収書を金融機関に提出し、教育資金口座から資金を引き出すことができる。
手続きが複雑であること以外の注意点としては、口座内の資金を使い切れなかった場合の処理が挙げられます。
まず、口座内に資金が残ったまま受贈者が30歳になった場合、残った資金は贈与税の課税対象となります。
※ 学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合(=要件A)は40歳
さらに、口座内に資金が残ったまま贈与者が死亡した場合には、残った資金は相続税の課税対象となります。
※ ただし、相続税の課税対象が5億円以下で、受贈者が23歳未満または要件Aを満たす場合は除く。
このように、他の制度と比べて少し複雑な制度となっているので、利用の際は専門家や口座開設先の金融機関にご相談ください。
その4:直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(結婚・子育て資金の一括贈与)
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(通称:結婚・子育て資金の一括贈与)とは、父母や祖父母などの直系尊属から、結婚・出産・育児のための資金を一括で贈与された場合に、最大で1,000万円(そのうち、結婚に関する資金については300万円まで)+基礎控除110万円まで贈与税が非課税となる制度です。
※ 「一括贈与」という制度名ですが、枠内であれば複数回に分けて贈与しても問題ありません。
詳しい要件は以下のとおりです。
「結婚・出産・育児のための資金」の要件は、以下のとおりです。
(参考:父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁)
このように、この制度は先ほど解説した「教育資金の一括贈与」とよく似た制度です。そして内容のみならず、利用のために必要な手続きも、教育資金の一括贈与とよく似ています。
その手続きの流れは、以下のとおりです。
- 贈与者と受贈者の間で贈与契約を締結し、贈与契約書を作成する。
→ 贈与契約書には、当事者双方の住所氏名・贈与する金額、贈与の予定日を記載し、当事者が署名押印します。なお、受贈者が未成年である場合は、法定代理人(親)が代わりに契約します。 - 金融機関で、受贈者名義の「結婚・子育て資金口座」を開設する。
→ 口座開設時には、①で作成した贈与契約書のほか、戸籍謄本等が必要です。詳しくは、各金融機関の案内を参照してください。 - 口座開設した金融機関に、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する。
→ 税務署への提出は不要 - 結婚・子育て資金口座に、結婚・子育て資金を預け入れる。
- 受贈者は、結婚・子育て資金を支払ったときに受け取った領収書を金融機関に提出し、結婚・子育て口座から資金を引き出すことができる。
こちらの制度も教育資金の贈与と同様に、口座内の資金を使い切れなかった場合には、贈与税や相続税がかかるというデメリットがあります。
まず、口座内に資金が残ったまま受贈者が50歳になった場合、残った資金は贈与税の課税対象となります。
さらに、口座内に資金が残ったまま贈与者が死亡した場合には、残った資金は相続税の課税対象となります。
近年、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与について、「制度利用者が少ないから廃止すべきでは?」という議論がなされています。
これらの制度の利用者が少ない理由としては、制度の複雑さが挙げられるでしょう。さらに、「受贈者側に兄弟姉妹がいる場合、その全員に贈与しなければ不公平感がある」「口座開設に1万円超の手数料がかかる」といった点も、制度利用を遠ざける原因となっています。
とはいえ、有効活用すれば「子ども(孫)の生活を援助したい」「少しでも多く生前贈与して相続税を減らしたい」といったニーズに応えられる制度ではあるので、利用を検討している方は専門家や金融機関へご相談ください。
その5:特定障害者に対する贈与税の非課税(特定贈与信託)
特定障害者に対する贈与税の非課税(通称:特定贈与信託)とは、特定障害者(特別障害者及び一定の精神障害者)のために信託契約を締結し、信託銀行等の受託者を通じて最大で6,000万円(特別障害者以外の特定障害者の場合、3,000万円まで)+基礎控除110万円まで贈与税が非課税となる制度です。
これまで紹介した他の制度とは異なり、特定贈与信託という信託契約を活用した制度になっている点が特徴です。信託契約では、委託者(財産を預ける人)・受益者(財産から生じる利益を受ける人)・受託者(財産を預かる人)が登場しますが、特定贈与信託では、障害がある方を受益者として、その親族が信託銀行等に財産を預け、信託銀行等がその財産を運用し、受益者に給付します。この仕組みのおかげで、委託者に万が一のことがあっても、障害のある受益者のために、受託者が資金を提供し続けることができるのです。
この信託は、受益者が亡くなるまで続きます。節税よりも受益者の生活のための制度である点が、他の制度との大きな違いです。
(参考:障害者と税|国税庁)
その6:相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属が18歳以上の子どもや孫へ贈与する場合に、毎年110万円の基礎控除に加えて累計で2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
ただし、この制度を利用した場合は、贈与された財産の価値を、相続発生時に相続財産として再度合算(精算)して相続税を計算しなければなりません。つまり、贈与時点では贈与税を軽減し、最終的には相続時に精算する仕組みといえるでしょう。
また、2,500万円の枠を超えた贈与については、一律で20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税制度について、詳しくはこちらの記事で紹介しています。
まとめ
贈与税は、個人から財産をもらった人に課される税金ですが、教育資金や住宅取得資金など、特定の目的にあてる場合には非課税となる制度が用意されています。
今回紹介した6つの制度(夫婦間贈与、住宅取得資金の贈与、教育資金・結婚子育て資金の贈与、障害者扶養信託、相続時精算課税)は、いずれも条件を満たせば大きな節税効果を得られます。
ただし、期限や要件を正しく理解せずに利用すると、贈与税が免除されず、かえって税負担が大きくなるリスクもあります。制度の内容を正確に把握し、専門家の助言を受けながら、無理のない形で財産を次の世代へ引き継ぎましょう。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。