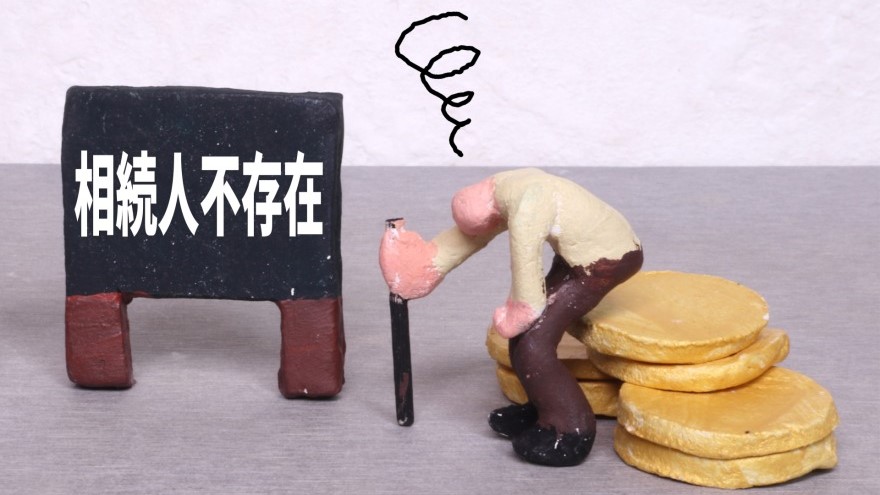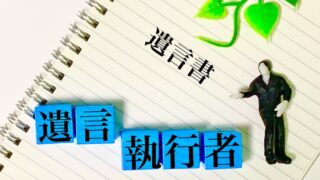「相続人がいなかったらどうなるのか」ということは、ご自分や身近な方がそのような状況にならないと中々考える機会がないことでしょう。このような状態を、相続人不存在といいます。こうしたケースでは、最終的にその財産は国のものとなる(国庫に帰属する)決まりになっていますが、それまでの過程には特別な手続きが必要です。
このような事態を避けたい場合には、生前に遺言や贈与などの対策が必要となりますが、どの対策にもメリット・デメリットがあり、どの手段がおすすめかは個別の事情によって異なります。
今回は、相続人不存在のケースでの財産処理の流れや、どのような対策が取れるのかについて、詳しく解説します。
相続人不存在とは?
相続人不存在とは、亡くなった方(被相続人)に法定相続人がおらず、遺言もないような状態を指します。
法定相続人とは、民法で決められた相続人のことであり、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの遺産を相続できる権利を持つ人々を指します。
通常、被相続人が亡くなると、その遺産は、法定相続人や遺言で指定された人(受遺者)が受け継ぎますが、以下のような場合には相続人不存在の状態になることがあります。
このような場合、相続人がいないため、遺産は特別な手続きのもとで処理されることになります。
相続財産が国庫に帰属するまでの流れ
相続人不存在の状態であっても、被相続人の財産をそのまま放置するわけにはいきません。
この場合、法律上、以下のような手順を踏んで財産の処理が進められます。
ステップ1:家庭裁判所への「相続財産清算人」選任の申立て
相続人がいない場合、まずは利害関係者や検察官が家庭裁判所に対して「相続財産清算人」の選任を申し立てます。
利害関係者とは、被相続人にお金を貸している債権者や、被相続人の不動産を管理している人等です。
家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると、相続財産清算人が相続財産を管理するようになります。相続財産清算人は、まず被相続人の財産を調査し、必要に応じて債務の弁済や不動産の処分を行います。そして最終的に相続財産が国庫に帰属するまで、必要な手続きを取るのです(相続財産清算人の役割について、詳しくは後述します)。
相続財産清算人は、2023年(令和5年)4月1日の民法改正で新しくできた役職です。
以前は相続財産管理人という名称でしたが、この改正によって名称が整理され、
相続財産管理人 → 管理のみを行う
相続財産清算人 → 管理・清算を行う
と、役割分担されたのです。
よって、従来の相続財産管理人と、現行法の相続財産清算人は、名称が異なるだけで、ほとんど同じようなものです。
ステップ2:相続人の探索
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は、6か月以上の期間を定めて公告を行い、相続人が名乗りでないかどうかの確認をします。
相続財産清算人が選任されている以上、戸籍などから相続人がいないことは確認されているでしょうが、最終確認としてこのような機会が設けられています。
ステップ3:債権者や受遺者への公告
相続人への公告のほかに、家庭裁判所は、2か月以上の期間を定めて、債権者や受遺者への公告を行います。これは、被相続人に対して債権を持っている人や、遺言によって財産を受け取る権利がある人に対して、名乗り出る機会を与えるものです。
公告は通常、裁判所の前に掲示する方法と官報公告(国が発行する官報という新聞のようなものに掲載する方法)が併せて取られますが、大手金融機関など以外の個人がこのような公告を見て名乗り出ることはほとんどありません。
ステップ4:特別縁故者への財産分与
相続人がおらず、借金の取り立てなどもなかった場合、家庭裁判所は「特別縁故者」と呼ばれる人に財産を分与することができます。
特別縁故者とは、亡くなった人と生前に特別な関係を持っていた人(例えば、内縁の配偶者や、老後の面倒を見ていた人物など)です。
特別縁故者として財産の分与を希望する人は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この申立てができる期間は、ステップ2やステップ3の公告が終わった後、3か月間と定められています。
ステップ5:国庫への帰属
債権者や受遺者、特別縁故者がいない場合、もしくはそれらの人たちへの清算手続きが終わった後、残った財産は最終的に国庫に帰属します。この際、相続財産清算人への報酬も清算されます。
相続財産清算人の役割とは?
以上のような過程で財産の清算が行われる間、相続財産清算人は、次のような仕事をしています。
相続財産は通常、相続財産清算人の判断に基づいて管理されますが、売却や廃棄などが必要となった場合には、家庭裁判所の許可を経て行われます。
相続財産清算人は、家庭裁判所の監督のもと、相続財産の管理や処分、保全をしているのです。
相続人がいない場合に取れる3つの対策
このように、相続人がいないまま何の対策もせずに亡くなってしまった場合、大掛かりな手続きが必要となってしまいます。
そんな手続きを避けたい場合や、自分の財産を国に渡したくない場合、どのような対策がとれるのでしょうか。対策の種類と特徴、メリット・デメリットを挙げていきます。
対策その1:遺言書の作成
遺言書を作成することで、特定の人や団体に財産を遺すことが可能です。遺言書には、自分が誰にどのような財産を相続させたいかを明記することができ、法定相続人がいない場合でも、自分の意思を遺すことができます。
なお、相続人のいない人が遺言書を書く場合は、遺言執行者を指定しておくと他界後の手続きがスムーズです。
メリット
デメリット
対策その2:生前贈与
生前に財産を希望する相手に贈与する生前贈与も、効果的な対策です。生前贈与では、自分が生きている間に財産を渡すため、遺される財産自体を減らすことができ、相続の問題を事前に回避できます。
メリット
デメリット
対策その3:信託の活用(遺言信託)
自分の財産を管理・運用するために、信託を利用することも一つの方法です。信託契約を結ぶことで、信頼できる第三者が財産を管理し、特定の目的に従って財産を分配することができます。
メリット
デメリット
財産の話とは別になりますが、相続人がいない方は、自分が亡くなったときの葬儀や病院代の支払い、施設の解約手続きなどを任せるために、信頼できる知人や友人、専門家などと「死後事務委任契約」を結んでおくこともおすすめします。
死後事務委任契約とは、文字どおり「死後に残った事務手続きをお願いする契約」です。
通常、委任契約は委任した側・された側のどちらかが死亡すれば効果がなくなってしまいますが、この契約は例外的に認められています。
ただし、実際に委任された側が手続きをするときには当事者が亡くなってしまっているので、効果を明確にするためにも公正証書で契約書を作成することをおすすめします。
まとめ
相続人がいない場合、何の対策も取らないと、財産は国庫に帰属します。そしてその過程で、家庭裁判所や相続財産清算人など、多くの第三者が関わることになります。
しかし、適切な対策を取ることで、自分の財産を希望する人や団体に財産を遺すことが可能です。遺言書の作成や生前贈与、信託の活用など、自分の状況に合わせた対策を講じましょう。
自分は対策が必要な状況なのか? どんなことができるのか? といった不安がある場合には、専門家に相談しながら、早めに見通しを立てておくことをおすすめします。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。