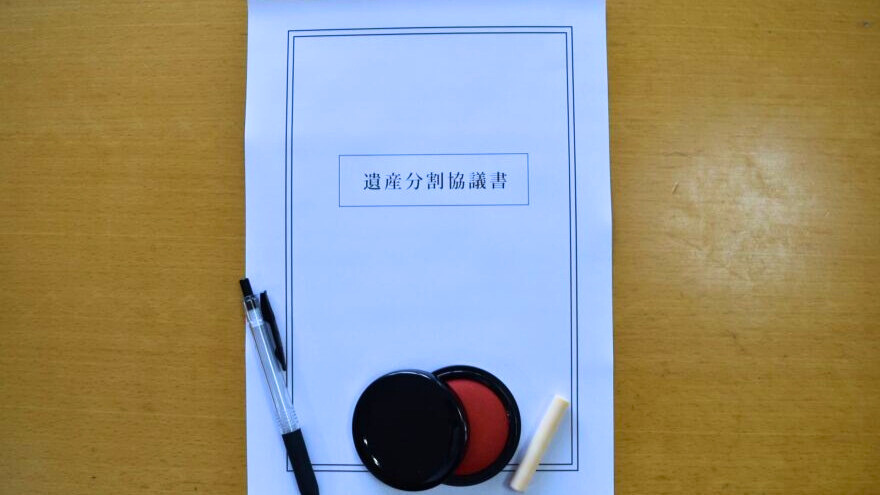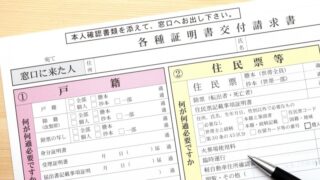「遺産分割」や「遺産分割協議」という言葉は、みなさんどこかで耳にしたことがあるでしょう。
遺産分割協議とは、相続が発生したあと(=被相続人が亡くなったあと)、相続人全員が集まって、被相続人の財産や負債を誰がどう引き継ぐかを話し合うことです。そして、その内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の解約に必要となるほか、後日の紛争を予防する役割もあります。
この記事では、そんな遺産分割協議書の役割や基本的な作り方、作成時の注意点などをわかりやすく解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書は、相続人全員で協議して決めた遺産の分け方をまとめた文書です。作成する際には、被相続人やその財産・負債等の内容を明確に特定できる書き方でまとめ、相続人全員で署名捺印をし、相続人全員の印鑑証明書を添える必要があります。
では、そもそも遺産分割はどのような場合に必要なのでしょうか?
相続が発生した場合、基本的に、財産の分け方は以下の順番で決まります。
- 遺言があれば、遺言どおりに分ける
- 遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をして決める
- 何もしなければ、法定相続分で分ける
このように、被相続人が遺言を残していない場合に、相続人全員で話し合って財産の分け方を決めるのです(ただし、遺言があったとしても、相続人全員・受遺者・遺言執行者で協議を行えば、遺言の内容に反する遺産分割協議をすることもできます)。
この場合において、単純な話合いで決まればその内容を遺産分割協議書にまとめますが、話合いで決まらなかった場合には、家庭裁判所での調停や審判といった裁判手続きになることもあります。この場合は、裁判所が話合いの内容をまとめることになります。
遺産分割協議書の作り方
では、遺産分割協議書はどのように作ればよいのでしょうか?
遺産分割の手順も含め、全体の流れをまとめていきます。
作成までの流れ・必要書類
被相続人が亡くなって遺言がなければ、遺産分割を進めていきます。タイミングとしては、葬儀や法要がひと段落し、遺産に関する手続きが必要となった時点で問題ありません。
ただし、相続放棄をしたいときは亡くなったことを知ってから3か月以内/特別受益を主張するには亡くなってから10年以内など、期限が定められている手続きもあります。
また、相続財産を放置しておくことで財産の内容が曖昧になったり、負債の利子がかさんだりするケースや、相続人と連絡がつかなくなることもあるので、できるうちに早めに終わらせておくことをおすすめします。
作成までの流れや必要な資料は、次のとおりです。
ステップ1:相続人を確定させる
まず、相続人を確定させましょう。相続人を確定させるには、被相続人の生まれたときから亡くなるまでの戸籍を調査する必要があります。そして、相続人となる人の現在戸籍・住民票(または戸籍の附票)も必要です。
誰が相続人になるか/具体的な戸籍の集め方は、以下の記事を参照してください。
ステップ2:被相続人の財産・負債を確認する
次に、被相続人の財産や負債を確認します。財産や負債としては、以下のようなものが挙げられます。
財産:不動産/銀行預金(普通預金・定期預金)/株式/投資信託/医療保険/年金/事業用資産など
負債:金融機関からの借入れ/消費者金融からの借入れ/住宅ローン(団体信用保険により完済されることも)など
確認するには、自宅にある不動産の権利書や通帳、被相続人の財布、保険証券、郵送物などを確認するほか、各機関から次のような資料を取り寄せます。
財産に漏れがあったり、相続人同士で財産の価値の認識に違いがあったりすると、後で争いになりかねないので、できる限り客観的な資料で確認するようにしましょう。
固定資産税評価証明書と名寄帳は、不動産を調査する際に取得することが多い資料です。
固定資産税評価証明書には、市区町村が定めた固定資産(土地や建物)の評価額が載っています。この評価額は3年ごとに見直され、時価のおよそ70%です。固定資産税や登記にかかる登録免許税は、この額を基準に計算します。
名寄帳には、毎年1月1日時点で申請者がその市区町村に所有している土地と建物の一覧が載っています。所有者が亡くなったときは相続人が取得できますので、不動産に漏れがないよう、請求して確認します。
どちらも市役所等の資産税課等の部署で発行していますので、「○○市 評価証明書」、「○○市 名寄帳」などで検索し、発行窓口を調べて取り寄せてください。
ステップ3:相続人全員で財産の分け方を決める(遺産分割協議をする)
相続人と相続財産がわかったら、相続人同士で話し合って分け方を決めます。
自宅などの不動産は住んでいる人がそのまま相続することも多いでしょうが、その場合、他の相続人とのバランスに注意しましょう。もちろん、他の相続人が納得すれば、お金も含めてすべてを一人で相続することも可能です。
また、不動産を共同で相続する場合(例:自宅を長男Aと次男Bが2分の1ずつ相続する。)、不動産の管理・売却は協力して進める必要があります。
このように、遺産分割時点で相続人全員が納得できるうえで、相続した後の手続きにも困らないような内容にになるよう心がけましょう。
ステップ4:遺産分割協議書を作る
内容が決まれば、遺産分割協議書を作成します。作成した協議書には相続人全員が署名・捺印(実印)し、各々の印鑑証明書を添付します。
原本は不動産の名義変更や銀行預金の手続きに使うので、財産を相続した人が保管すると便利です。まったく同じ協議書を相続人の人数分作成して、各自で保管しておくとより安心でしょう。
次のようなケースでは、たとえ相続人であっても、署名・捺印をすることができません。
① 相続人が認知症であり、遺産分割協議をするために必要な判断が困難な場合
→ 認知症の相続人は、遺産分割協議に参加することができません。この場合には、成年後見制度の利用を検討することになります。
② 相続人が18歳未満の未成年者である場合
→ 未成年者は単独で法律行為をすることができず、遺産分割協議に参加することはできません。このような場合には、親権者が代わりに参加するか、特別代理人を選任する、もしくは成人するまで待つ必要があります。
③ 相続人が海外に居住しており、印鑑を登録できない場合
→ 海外には印鑑文化がない国がほとんどであり、海外に居住している相続人は、一般的に、印鑑証明書を取得することができません。このような場合には、別途「署名証明書(サイン証明書)」で対応する必要があります。
記載する項目
遺産分割協議書には、以下の項目を記載します。
重要なのは、「誰が読んでも財産の内容と分け方が明確にわかるように書くこと」です。記載内容が不明確だと、銀行などから受付を拒否されて預金の解約などの手続きができない恐れもあります。
とはいえこれらの項目はあくまで一般的なものであり、遺産分割協議書の記載方法について細かい法律上の決まりはなく、上記の項目が欠けていても、それだけで遺産分割協議書が無効にはなりません。しかし、客観的に見て内容が明確でないと後のトラブルにも繋がりかねないため、上記の項目を盛り込んで極力明確に書くよう心がけましょう。
記載例(一部抜粋)
下記被相続人の遺産について、相続人全員で次のとおり協議を行い、合意した。
被相続人 A
生年月日 昭和◯年◯月◯日生
死亡日 令和◯年◯月◯日死亡
本 籍 ◯◯市◯◯町◯丁目◯番
住 所 ◯◯市◯◯町◯丁目◯番第1条 下記不動産は、相続人Bが相続する。
所在:大阪市◯◯区◯◯町◯番◯
地番:◯◯
地目:宅地
地積:◯◯㎡第2条 下記預貯金は、相続人Cが相続する。
◯◯銀行 ◯◯支店 普通 口座番号 0000000
……
上記内容に相違ないことを確認のうえ、これを証するため本書を作成し、署名・押印のうえ保管する。
相続人B
住所
署名 印相続人C
住所
署名 印
遺産分割協議書の使い道
作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金・株式等の解約、自動車の名義変更、相続税の申告などに必要となります。また、どのような協議をしたか記録しておくことで、後日の紛争を予防することもできます。
さらには、二次相続(相続人が亡くなることで発生する相続/次の相続)の資料になることもあるので、手続きが終わったあとも大切に保管しておきましょう。
作成時の注意点
最後に、作成時の注意点をいくつか挙げていきます。
まとめ
遺産分割協議書は、相続手続きのあらゆる場面で必要となる重要な書類です。やり直しや後日の紛争を防ぐためにも、戸籍や住民票、財産の資料などをもとに、遺産の内容と分け方を明確に記載しましょう。
内容に不安がある場合や、相続関係が複雑なときは、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、手続きの不備やトラブルを防ぐことができます。
相続は一度きりの重要な手続きです。確実で円滑な遺産分割のために、正しい知識と準備を整えておきましょう。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。