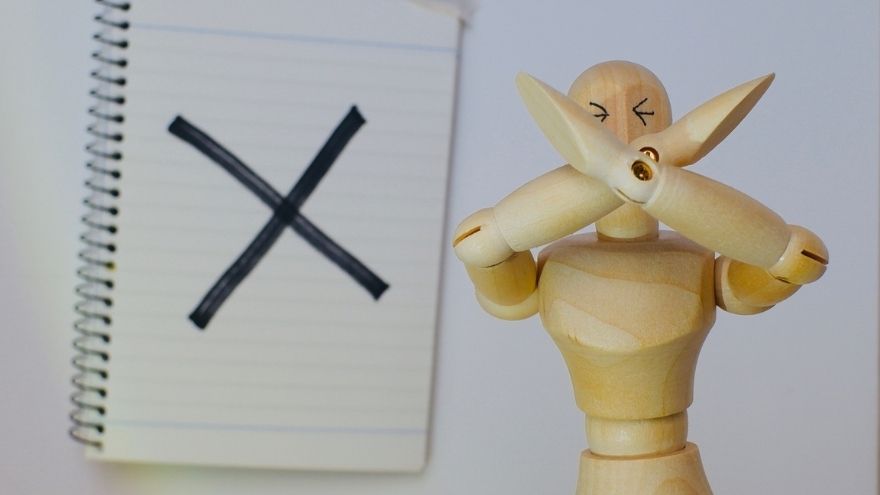「相続」というと一般的に、亡くなった方の財産を引き継ぐイメージがあるでしょう。しかし実際には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
こうした状況で選べる選択肢の一つが相続放棄です。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくて済むようになります。
しかし、相続放棄は一度してしまうと取り消すことができず、期限や要件も厳格に定められている複雑な手続きです。このような手続きが自分に必要かどうかを、突然の他界で多額の借金を背負うかもしれないという追い詰められた状態で、冷静に検討するのは難しいことでしょう。
この記事では、そのような状況の方に最低限知っていただきたい相続放棄の基本的な仕組みやメリット・デメリットなどを解説しています。今悩まれている方はもちろん、将来的に相続放棄を検討されている方にも参考になれば幸いです。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄する手続きであり、この手続きをすることで、亡くなった方(被相続人)の一切の財産・負債を相続しないことになります。
相続放棄をするには、原則として、被相続人が亡くなって自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄したい旨を申述しなければなりません。この3か月という期限を過ぎてしまうと、相続を認めたものとみなされ、被相続人の一切の財産・負債を引き継ぐことになります(これを「単純承認」といいます)。
相続放棄を検討した方がよいのは、以下のようなケースです。
このような状況においては、相続人という立場の一切を放棄できる相続放棄という手段は、非常に有効です。さらに、相続放棄は他の相続人と話し合わずに1人で進めることができる点でも非常に便利な制度といえるでしょう。
しかし、そんな利便性がある一方で、一度相続放棄をしてしまうと取り消すことはできないという厳格な制度でもあります。これから解説するメリット・デメリットや注意点をよく検討したうえで、少しでも不安であれば専門家に依頼して進めるようにしましょう。
すべての財産を相続する単純承認以外の手段として、相続放棄のほかに、限定承認という手段があります。
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を引き継ぐことです。
つまり、被相続人の資産が負債より多ければ負債を返済して余った資産を引き継ぐことができ、被相続人の資産が負債より少なければその資産で返せる範囲で負債を返済して、残った負債は引き継がれません。
限定承認は、「借金がいくらあるかわからない」場合や、「借金は多いが実家を手放したくない」場合に有用な手段です。借金が想定より多くともその返済義務を負うリスクがなくなりますし、実家を競売にかけるときに先買権という権利を行使して実家を買い戻すことができます。
限定承認も相続放棄と同様、被相続人が亡くなり自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただし、相続放棄とは異なり、限定承認は相続人全員で行わなければならず、裁判所での手続きも複雑です。
この複雑さからあまり利用されておらず、相続放棄が年間20万件弱あるのに対し、限定承認は年間1000件程度しかありません。ご検討の際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄と似た言葉に、財産放棄があります。これは法律用語ではありませんが、一般的には、すべての財産をもらわないという意思表示をすることを指す言葉として使われており、「遺産分割」や「相続分の譲渡」といった手段で行われます。
これは相続放棄のように相続権のすべてを失うものではないので、特に期限は定められておらず、家庭裁判所での手続きも不要です。
ただし、あくまで相続人の1人ではあり続けますので、遺産分割協議書や相続分の譲渡証明書等の書類への署名押印などが求められます。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄をすると、「相続人ではなかったことになる」という強い法的効果が得られます。その強さゆえにメリットがあると同時に、デメリットもありますので、手続きをしてしまう前によく検討しましょう。
メリット(上記「相続放棄とは?」参照)
デメリット
相続放棄の4つの注意点
ここまで相続放棄の概要を確認しましたが、次に、相続放棄を検討するにあたって特に注意したい点をまとめていきます。
注意点1:期限内に手続きを行わなければならない
相続放棄は、「被相続人が亡くなり、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。
ただし、実際の裁判所の審査では亡くなってから3か月を過ぎていたら審査が厳しくなり、「本当に知らなかったのか?」「どういったタイミングで知ったのか?」を示す資料を提出しなければなりません。
例えば、被相続人と疎遠であった場合、被相続人の他界から3か月以上経ってから届いた書類などで相続の発生を知ることもあるでしょう。このようなケースでは、その書類が届いた日を示せるもの(書類の作成日や到達日が分かる資料)を裁判所に提出します。
とはいえ、3か月では財産の調査や鑑定評価が終わらず、相続放棄をすべきか判断できないこともあるでしょう。そのような場合には、期間を延ばすよう家庭裁判所にお願いすることもできます。このような手続きを、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」と呼びます。相続を承認すべきか放棄すべきか、ゆっくりと考えたいときは、忘れずにこのお願いをするようにしましょう。
注意点2:相続財産を使ってはいけない
相続財産(被相続人が遺した財産)を相続人が使うと、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
ここにいう「使う」とは、単にお金を自分のために使うのはもちろん、財産を隠したり、預貯金を解約したり、不動産を譲渡したりといった、処分・隠匿・消費等のすべての行為が該当します。
相続放棄の予定があるときは、相続財産には手をつけないよう注意してください。生前に住んでいたアパートの解約や滞納していた税金の支払いなども含め、すべての財産関係・契約関係に関わらないようにしましょう。
被相続人の財産に手をつけてはいけない一方で、「葬儀費用だけでも被相続人の貯金から支払いたい」ということもあるでしょう。
実務上の運用としては、葬儀費用は、一般的に許容できる程度の金額であれば、被相続人のお金から支払っても問題ありません。
しかし、過度に高額であったり、生前に利用していた病院代や施設利用料を含む場合には、単純承認とみなされかねません。不安であれば、支払ってしまう前に、必ず専門家に相談するようにしましょう。
注意点3:放棄した後の相続人が誰になるかを知っておく
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになり、相続をする権利は、次の相続人に移ります。たとえば、妻・子・兄がいるAが亡くなった場合に子が相続放棄をすると、相続権が兄に移り、妻と兄が相続人になります。
このような場合に、事前に相続権が誰に移るかを知らなければ、「兄には知られたくなかったのに…」「兄を巻き込むつもりはなかったのに…」といった事態に発展しかねません。事前に次の相続人を把握しておくことで、このような想定外の事態を防ぐことができます。
また、相続放棄をした場合、代襲相続が起こらない点にも注意が必要です。たとえば、妻・子・孫がいるAが亡くなった場合に子が相続放棄をしても、孫は相続人にはなりません。なぜなら、子は相続放棄により初めから相続人ではなかったことになるため、その子である孫も相続と無関係になるからです。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになるため、相続人全員が相続放棄をして、相続人がいなくなるケースも起こり得ます。
このような状態を相続人不存在といいます。
相続人不存在の状態になると、相続財産は被相続人の債権者や、被相続人と関わりが深い人(特別縁故者)に分配され、それでもなお余った財産は最終的に国庫に帰属します。
注意点4:相続放棄をしても管理しなければならないものもある
相続放棄をしても、相続財産を所持・管理している場合には、新たな相続人または相続財産清算人に引き継ぐまでの間、その財産を管理しなければなりません。
特に被相続人名義の不動産に居住している場合には、注意が必要です。
相続放棄にかかる費用
相続放棄にかかる費用は、「必ずかかる費用」と「専門家に依頼する場合の報酬」にわけられます。
自分で手続きをする場合には「必ずかかる費用」だけで済みますが、専門家に手続きを依頼する場合、追加でその報酬が発生します(専門家に依頼すべきかどうかの判断基準は、上記「特に注意したい点」を参考にしてください)。
なお、相続放棄にかかる費用を相続財産から支払うことはできません。支払ってしまうと相続放棄ができなくなるおそれがあるので、必ず自己負担で支払うようにしてください。費用にお困りの場合は、法テラスのご利用もご検討ください。
必ずかかる費用
必ずかかる費用は、家庭裁判所への申立てに必要な費用です。
総額数千円程度で、内訳は以下のとおりです(必要な書類の詳細は、後記「手続きの流れ」で解説しています)。
専門家に依頼する場合の報酬
相続放棄の手続きは、弁護士または司法書士に依頼することができます。
ただし、弁護士は「代理人」として依頼者の代わりに書類を作成するのに対し、司法書士は「書類作成代行者」として依頼者の書類作成をサポートする立場にあります。その立場の違いから、報酬の相場は弁護士の方が比較的高額になっています。とはいえ、相続人同士が対立しているような場合や、すでに訴訟になっている場合は、紛争解決のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。
手続きの流れ
では次に、相続放棄をすると決めた場合に、実際にどのような流れで手続きが進むのかを解説します。
1 相続財産を調査する
はじめに、被相続人の財産を調査します。プラスの財産とマイナスの財産、どちらも漏れなく調査するようにしてください。心理的な面から、本人が誰にも話していないことも多いので、「これで全部だろう」と思わずに細かく調査をするようにしましょう。
被相続人の債務とその手がかりとして、以下のようなものが考えられます。
このように、確認の方法はいくつかありますが、実際には相手方から請求や督促がこない限りわからない債務も多いです。知らない借金についていきなり連絡がきたときは、慌てて支払わず、落ち着いて詳細を確認するようにしましょう。
さらに、念のため、各信用情報機関(JICC、CIC、KSC)へ信用情報の開示請求をすることをおすすめします。信用情報機関には、過去5年間の借入れの履歴などの債務に関する情報が登録されています。相続人であれば戸籍や本人確認書類を提出することで開示請求ができますので、調べておくと安心です。
ただし、どの信用情報機関にも登録されない債務(保証債務、個人間の借金、公共料金や税金の滞納)もあります。信用情報機関への問い合わせでおおむねの債務は確認できますが、遺品の捜索もあわせて行う必要があるのです。
2 必要書類を集める
次に、家庭裁判所に提出する必要書類を集めます。
必要な書類は、裁判所のホームページに記載されている以下の書類です。
3 家庭裁判所に書類を提出する(=相続放棄の申述)
2で揃えた必要書類を、家庭裁判所に提出します。
提出先は、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。
この提出は、先ほど解説した3か月の熟慮期間内に行わなければなりません。期限が過ぎてしまわないよう気をつけましょう。
4 家庭裁判所からの照会書を返送する(届いた場合のみ)
審査の途中で、家庭裁判所から確認の照会書が届く場合があります。照会書の目的は、主に相続放棄の意思確認です。よく読んで必要事項を記入し、返送してください。
また、最初に提出した書類に不備があれば、対応を求められることもあります。手続きをしている間は、裁判所からの連絡にはすぐに対応できるようにしておきましょう。
5 相続放棄受理通知書が届く
家庭裁判所での審査が完了すれば、「相続放棄受理通知書」が届きます。これによって、正式に相続放棄が認められたことになりますので、大切に保管するようにしてください。
なお、相続放棄が完了しても、被相続人の債権者(生前に借入れをしていた金融機関など)に通知などがされるわけではありません。そのため、相続放棄をした後にも返済を求められることがあります。そのような場合には、この「相続放棄申述受理通知書」を提示して、相続放棄をしている旨を伝えてください。
金融機関によっては、別途「相続放棄申述受理証明書」の提示を求められることもあります。こちらは裁判所で発行できるので、必要があれば発行しておくようにしましょう。
また、可能であれば、次に相続人となる方に相続放棄をした旨を伝えることをおすすめします。先述のとおり、相続放棄をすると、相続人の地位は次の相続人に移ります。その方が知らない間に借金を背負うことなどがないよう、連絡してあげましょう。
まとめ
相続放棄は、相続人としての地位を放棄する、とても強力な制度です。故人が遺した借金を背負いたくない場合、必須の手続きといえるでしょう。
一方で、相続放棄には、「プラスの財産を受け取れない」「他の相続人にも影響してしまう」といったデメリットや、「期限を必ず守らなければならない」「一度相続財産に手をつけてしまうとできなくなる」といった厳密な要件もあります。また、一度相続放棄をしてしまうと撤回することはできません。必ずメリット・デメリットをよく吟味し、制度を理解したうえで手続きをするようにしてください。
ご自身が相続放棄をするべきかどうか、ご不安のある方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。特に期限を過ぎてしまった方や、多忙のために手続きの時間をとることが難しい方は、速やかに専門家への相談をご検討ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。