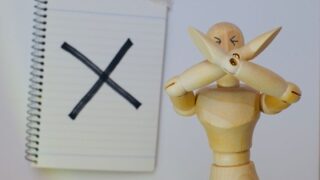不動産を含む財産の相続放棄を検討するとき、気になることのひとつが固定資産税を支払う必要があるかどうかという点でしょう。
相続放棄は、不動産を含む一切の財産・負債を相続しないようにする手続きです。そして固定資産税は、不動産を所有している人に毎年かかる税金です。
このような性質から、
「相続放棄をすれば固定資産税は支払わなくていい?」
「相続放棄前だが、被相続人(亡くなった人)名義の固定資産税を支払ってしまっても大丈夫?」
「かなり前に相続放棄をしたのに納税通知書が届くのはなぜ?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、このような疑問に答えるため、相続放棄と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。
用語の確認
まずは相続放棄と固定資産税について、簡単に解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄する手続きであり、この手続きをすることで、亡くなった方(被相続人)の一切の財産・負債を相続しないことになります。
相続放棄をするには、原則として、被相続人が亡くなって自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄したい旨を申述しなければなりません。この3か月という期限を過ぎてしまうと、相続を認めたものとみなされ、被相続人の一切の財産・負債を引き継ぐことになります(これを「単純承認」といいます)。
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物、一定の償却資産などの固定資産に対して課せられる地方税です。毎年1月1日時点の所有者に納付義務があり、毎年4月頃に納税通知書が届きます。
税額は、土地や建物の固定資産税評価額の1.4%ですが、築年数や場所によって調整されています。
相続と固定資産税
以上のような性質から、不動産を相続して名義変更(相続登記や税務署への届出)をすると、次の1月1日から新しい所有者に固定資産税が課せられます。
それでは、相続放棄をして一切の財産を引き継がない場合、どうなるのでしょうか?
相続放棄をすれば固定資産税を支払わなくていいが・・・
結論として、相続放棄をすれば固定資産税の支払義務はなくなります。
ただし、相続放棄がされた旨は役所には通知されませんので、以下のような理由で相続放棄をした後も納税通知書が届くことがあります。
このような場合に納税通知書を無視し続けると、督促が続くだけではなく、最悪の場合、差押えなどの法的手続きに進みかねません。
そうなる前に、次のような対応をしてください。
相続放棄をした後に納税通知書が届いたときの対処法
相続放棄をした後に納税通知書が届いたときの対処法としては、次のようなものがあります。
対処法その1:役所に連絡して、相続放棄した旨を伝える
まずは納税通知書の送り主である役所に連絡して、相続放棄をしている旨を伝えます。その際、相続放棄をした証明として「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められる可能性があるので、準備しておきましょう。
役所によってはこの時点で納税義務を免除する手続きをしてくれますが、原則として、納税通知書が届いた人(1月1日時点で納税義務者として登録されている人)には、支払義務があります。
支払わなければならなくなった場合の対処法としては、次の2つがあります。
→ 代わりに支払って、後から本来の相続人に請求する(事後求償)
1つ目の方法は、納税通知書のとおりに支払い、後から本来の相続人に請求する方法です。
これは、他に相続人がいる、または次順位の相続人(相続権は、子→親→兄弟の順で移動します)がいる場合の手段です。
メリットとしては「納税義務をきちんと果たせるため、延滞税が加算されず、差押え等の法的措置も受けない」ことです。
一方、デメリットとして、「後から請求しても回収できない可能性がある」ことが挙げられます。請求先は2つあり、① 他の相続人が相続した場合にはその相続人に、② 相続人が誰もいない場合には家庭裁判所が選任した相続財産清算人に請求しますが、どちらの場合にも回収できない可能性があり、特に後者については相続財産清算人の選任までにかかる費用の方が高額になることもあります。前者の場合、できれば支払ってしまう前に本来の相続人に連絡をして、立て替える旨を伝えておきましょう。
→ 課税処分を取り消すよう不服申立てをする
2つ目の方法は、課税処分を取り消すよう、役所の決定に対して不服申立てをする方法です。
不服申立ては、管轄の市区町村長に行います。不服申立てが認められれば課税処分は取り消されますが、不服申立てが認められるには、「課税処分に法的根拠がないこと」と「納税通知書が届いてから3か月以内に申立てをしていること」が求められます。
ただし、1月1日時点で新たな所有者への名義変更が終わっていない場合、法的根拠がないとはいえないので、認められないことが多いでしょう。
対処法その2:相続放棄をしていない相続人に名義変更をしてもらう
役所とのやり取りで解決しなければ、新しい所有者となる相続人に連絡し、名義変更(相続登記)をするよう促します(連絡しなくても問題はありませんが、名義変更が終わらない場合、引き続き納税通知書が届き続けてしまう可能性があります)。
ただし、1月1日以降にすでに名義変更をしている場合や、相続手続きに手間取っている可能性もありますし、相続が開始したことを知ってその相続人も相続放棄を検討することもあるので、伝え方には注意しましょう。
相続放棄をする前に固定資産税を支払っても大丈夫?
一方、相続放棄をする「前」はどうでしょうか。
相続放棄は、被相続人の一切の資産・負債を引き継がない手続きです。そのような強い法的効果が得られる手続きである一方、要件が厳しく、相続放棄をする前に被相続人の資産を使ってしまうと、相続したものとみなされてしまい、原則として相続放棄ができなくなります。
このようなルールがあるため、相続放棄をする前に相続財産から固定資産税を支払ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるのです。
相続放棄の前に固定資産税の納税通知書が届いた場合には、慌てて支払わず、まずは相続放棄の手続きを優先してください。
もしも先に支払う必要があれば、相続財産には手をつけず、必ず自分のお金で支払うようにしましょう。
年内に相続放棄をしたのに固定資産税を支払ってしまったら?
1月1日までに名義変更を終えていても、役所内の手続きの関係で、固定資産税の納税通知書が届いてしまうことがあります。
このような場合に固定資産税を支払ってしまったときには、本来の所有者に請求するほか、役所に対しての還付請求が認められる可能性があります。
還付請求は、納期限の翌日から5年以内に行わなければなりません。ハードルが高い手続きではありますが、検討の余地があれば弁護士等の専門家に相談してください。
相続放棄をせずに不動産を手放す方法としては、次のような方法が考えられます。
- 一度相続してから売却する
→ よく選択される方法ではありますが、売却できないリスクがあるので、売却先を見つけてから相続登記を進めることをおすすめします。 - 相続土地国庫帰属制度を利用する
→ これは、2023年4月に始まった国の制度であり、相続した不要な土地が一定の要件を満たしていれば、国が引き取ってくれるというものです。土地の要件として「更地であること」「境界が明確なこと」「土壌が綺麗なこと」「斜面や崖っぷちではないこと」などが細かく規定されていますが、近年は引き取りが認められているケースも増えています。
まとめ
相続放棄をすると、不動産を含む被相続人の財産をすべて引き継がないことになるため、固定資産税の納税義務はなくなります。しかし、相続放棄をした事実は役所には共有されないため、相続放棄後しばらくしても固定資産税の納税通知書が届く場合があります。
1月1日までに相続放棄を終えたにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、すぐに役所に相続放棄した旨を伝えるようにしましょう。
また、「今から相続放棄をする」予定の場合には、固定資産税を支払ってしまうことで相続放棄ができなくなる可能性もあります。対応にご不安のある方は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。