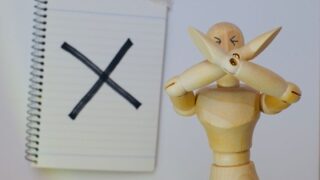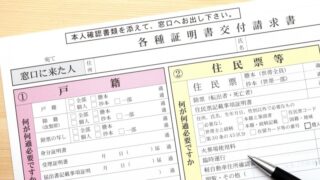相続では、亡くなった人(被相続人)のすべての財産が相続人に引き継がれますが、その際には、プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継がれます。
被相続人に多額の負債があると分かっている場合には「相続放棄」を選択することが一般的ですが、相続放棄をするとプラスの財産もすべて失ってしまうというデメリットがあります。また、資産と負債のどちらが多いのかがよくわからず、相続放棄を迷うケースもあるでしょう。
そこで検討できる選択肢の一つが「限定承認」です。限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済し、残りがあれば受け取ることができる制度です。利用例はあまり多くありませんが、特定のケースでは非常に有効な手段となります。
今回は、限定承認の概要や相続放棄との違い、メリット・デメリット、手続きの流れを詳しく解説します。
限定承認とは?
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈を弁済する方法です。
簡単に言えば、相続財産のプラスとマイナスを精算して、プラスが残れば受け取り、マイナスが多ければ自分の財産からは払わなくてよいという制度です。
具体例で考えてみましょう。被相続人が1,000万円の現金と700万円の借金を遺して他界したとします。この場合に限定承認をすれば、現金1,000万円のなかから借金700万円を返済し、相続人は、残り300万円を受け取ることができます。一方、同様の事例で借金が1,200万円であれば、資産の範囲内(1,000万円)で返済し、残った200万円の借金は相続人には引き継がれません。
相続放棄との違い
相続放棄と限定承認は、いずれも多額の借金を抱えた相続に直面したときに検討される制度です。
どちらも家庭裁判所を通じて行う手続きである点や、相続開始を知った日から3か月以内に申述しなければならない点で共通していますが、その内容は大きく異なります。
相続放棄と限定承認の3つの大きな違いは、以下のとおりです。
- 財産の取扱い
→ 相続放棄では、そもそも相続人ではなくなるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取ることはできない。
→ 限定承認では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金、ローンなど)を返済し、残りがあれば受け取ることができる。一方で、マイナスの財産の方が多くても、相続人が借金を引き継ぐことはない。 - どのような場合に選ばれるか
→ 相続放棄は、マイナスの財産の方が明らかに多い場合に検討される。
→ 限定承認は、財産の全貌が不明な場合や、プラスの財産の中に手放したくないもの(ご自宅など)がある場合に検討される。 - 手続きの当事者
→ 相続放棄は、各相続人が単独でできる。
→ 限定承認は、相続人全員が共同で行う必要がある。
このように、限定承認は財産の全貌がわからない場合や必ず相続したい財産がある場合に有効ですが、「相続人全員の協力がないと手続きができない」という大きなデメリットがあります。
限定承認では手放したくない財産を相続できる?
ここで、「プラスの財産の中に手放したくないものがある場合に限定承認が有効である」という記載に違和感をもたれた方もいるでしょう。
本来、限定承認では、マイナスの財産が多ければ、プラスの財産は一切受け取れません。しかし、限定承認では先買権という権利が認められており、その権利を行使することで、特定の財産を守ることができるのです。
先買権とは、相続財産を競売にかけて売却する際に、相続人がその競売に優先的に参加できる権利です。この権利を使えば、不動産や特定の事業用資産など、どうしても競売にかけられたくない財産を優先的に購入することができます。
ただし、この購入にかかる資金は相続人が自分で用意する必要があるため、ある程度の資金を準備しておきましょう。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認の概要がわかったところで、限定承認のメリット・デメリットを確認します。
メリット
デメリット
限定承認にかかる費用
限定承認の手続きには、主に以下の費用がかかります。
実務では、公告や財産目録作成などを含め、裁判所とのやり取りが煩雑なため、多くの方が専門家に依頼しています。
限定承認の手続きの流れ
限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
ステップ1:財産・負債・相続人を調査する
まずはプラスの財産とマイナスの財産、そして相続人を調査します。
被相続人名義の財産を調べるには、自宅に残された通帳や証券会社から届く書類、不動産の権利証などを確認しましょう。負債については、通帳に残された取引履歴や、財布のなかのカードなどから確認できます。また、信用情報機関(CIC、JICCなど)から信用情報を取り寄せるのも有効です。
各金融機関や消費者金融などは、相続人から問い合わせれば、残高を開示してくれます。ただし、借入がある金融機関等に問い合わせる際には、「借金がある」ことを認めてしまわないよう注意してください。相続人が被相続人の借金を認めてしまうと、相続放棄や限定承認が認められなくなる恐れがあります。
また、限定承認の手続きが終わるまでの間に相続財産を使ってしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄・限定承認ができなくなります。相続財産には一切手を付けないよう注意してください。
相続人の調査は、市区町村役場に戸籍を請求して行います。戸籍の集め方については以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
ステップ2:相続人全員の合意を得る
限定承認は、相続人全員で行う必要があります。限定承認を検討する際には、ステップ1で調べた資料等を相続人間で共有し、よく話し合って合意を形成してください。
話し合いが難しい場合や限定承認について詳しく説明してほしい場合などは、できるだけはやくお近くの弁護士や司法書士にご相談ください。
ステップ3:必要書類を準備する
限定承認をすると決めたら、次は家庭裁判所に提出する書類を準備します。
準備する書類は「限定承認の申述書(当事者目録・財産目録を含む)」と「ステップ1で集めた相続関係がわかる戸籍一式」です。
必要書類の一覧や書類の書き方は裁判所の公式サイトにまとめられているので、ご参照ください。
ステップ4:家庭裁判所に申述する(相続開始を知った日から3か月以内)
必要書類が整ったら、いよいよ家庭裁判所に提出します(限定承認の申述)。
ただし期限が定められており、この申述は、相続開始を知った日(=被相続人の死亡を知った日)から3か月以内にしなければなりません。
もし財産の調査などに時間がかかって期限を過ぎてしまいそうなときは、期間の伸長もできますが、その場合にも家庭裁判所での手続きが必要です。忘れずに伸長の手続きをするようにしましょう。
ステップ5:把握している債権者への通知・知らない債権者への公告
家庭裁判所で限定承認の申述が受理されると、債権者を探す手続きが始まります。
まず、すでに把握している債権者には、裁判所から「○○さんが亡くなって限定承認が始まりました。債権の詳細を教えてください。」という手紙が送られます。
そして、他に債権者がいないかどうかを調べるために、「○○さんが亡くなって限定承認が始まりました。○○さんに債権がある方は2か月以内に名乗り出てください。」という旨の官報公告がなされます。官報とは、国が発行する情報誌のようなものです。官報公告を掲載するには、4~5万円ほどの費用がかかります。この公告により、これまで把握されていなかった債権者に、申し出る機会を与えるのです。
以上の手続きで名乗り出なかった債権者は、これ以上被相続人に対して債権を主張できなくなり、限定承認の手続きから除外されます(ただし、後から発覚した債権者であっても、裁判所の判断によっては弁済を受けられる可能性もあります)。
ステップ6:相続債務の換価・弁済
公告が終了したら、プラスの財産を換価し、マイナスの財産を弁済する手続きに移行します。
換価は基本的に「すべての財産を現金化する」方法で行われます。この際、不動産等の資産があれば競売にかけられますが、相続人は先述のとおり先買権を行使して、これらの資産を買い取ることができます。
そして、マイナスの財産の弁済は、現金化された資産の範囲で行われます。相続人が負担する必要はありません。
ステップ7:残余財産の分配・名義変更
すべてのマイナスの財産を弁済してもなおプラスの財産が残っていれば、相続人にその財産が分配されます。
分配された財産については、一般の相続手続きに則って名義変更が必要です。相続人全員で遺産分割協議をして、相続登記などの名義変更手続きを進めましょう。
その際、相続した財産が相続税の基礎控除額を超えていれば相続税の申告が必要となります。
ここまでの手続きには、一般的に半年弱程度かかります。財産の内容が複雑な場合や権利関係に争いがある場合にはより長引く可能性もあるので、注意が必要です。
限定承認は、相続放棄と同様、被相続人に負債が多いときに選択される手続きです。しかし、相続放棄と比較して限定承認を選ぶ人は圧倒的に少ないのが現状であり、相続放棄が年間20万件程度行われているのに対し、限定承認は年間700件程度にとどまっています。
これは、相続人全員で行わなければならないことや手続きが煩雑なこと、費用が高額なことなどの、限定承認のデメリットによる結果でしょう。
このように事例が少ないため、専門家であっても限定承認を経験したことがない方も多くいます。
まとめ
限定承認は、相続財産の全貌が不明な場合や、特定の財産を残したい場合に有効な制度です。
一方で、相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑というデメリットもあります。制度の仕組みや相続放棄との違いを正しく理解し、期限内に手続きを進めるようにしましょう。
「相続放棄か限定承認か迷っている」「限定承認をしたいが、我が家の場合どのようなデメリットがあるか心配」という方は、ぜひお早めに弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。