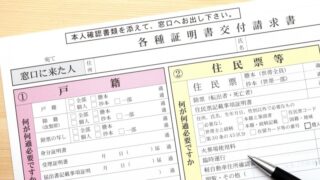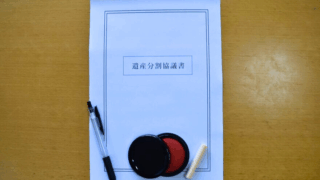相続によって不動産を取得した場合、本来は速やかに名義変更(相続登記)を行う必要があります。しかし、「すぐに売るわけじゃないから」「面倒だから」と、先延ばしにする方も少なくありません。
相続による家の名義変更を放置すると、売却や担保設定ができなくなるだけでなく、将来的に相続人が増えて手続きが極めて複雑になるおそれがあります。さらに、2024年(令和6年)4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に手続きをしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
本記事では、相続登記をしないことで生じる具体的なリスクや、相続登記の義務の内容について詳しく解説します。
相続した不動産の名義を放置する5つのリスク
さっそくですが、家や土地といった不動産を相続したときに、その名義変更(相続登記)をしないとどのようなリスクがあるか、いくつか挙げていきます。
リスクその1:不動産の売却や担保設定ができない
まず大きなデメリットとして、不動産を売ったり、不動産を担保にお金を借りたりといった取引行為ができないことが挙げられます。
不動産に関する取引をするときは、必ずその不動産の権利状態を示すための「登記」をします(売買であれば所有権移転登記・担保権の設定であれば抵当権設定登記等)。
この登記は、その取引をした現在の所有者が行わなければならず、亡くなっている名義人からすることはできません。つまり、相続登記をせずに不動産の名義を故人のままにしておくと、不動産に関する取引行為ができず、いざというときに不動産を売ったりローンを組んだりしてお金を工面することができなくなってしまうのです。
「今は売らないから大丈夫」と思っていても、この先の人生で何が起こるかわかりません。相続登記は放置するほど複雑化し、時間がかかるようになっていきます。不動産を相続したらすぐに相続登記をして、今後のお金の備えをしましょう。
リスクその2:相続登記の手続きが複雑化し、時間と費用がかかる
さきほど、「相続登記は放置するほど複雑化する」といいましたが、次に挙げるリスクはこの部分です。
相続登記は、相続人全員の協力がないとできません(例外として、裁判手続きによる強制的な相続登記もありますが、かなり稀です)。この点、相続登記を10年、20年と放置し続けると、相続人が亡くなって次の相続が発生し、関係者がどんどんと増えていきます。
私も明治大正時代の名義のまま放置されている土地を見たことがありますが、相続人は50人弱にまで増えていました。その全員に連絡を取って署名や捺印をお願いする作業は、非常に労力がかかることが目に見えるでしょう。
このような事態にならないためにも、相続した不動産はすぐに名義変更し、先の世代に手間をかけないようにしておきたいです。
リスクその3:所有者としての権利を第三者に主張できない
次は法律上の権利に関するお話です。不動産を相続して名義を変えないでいると、本来の所有者であるはずの相続人が、その不動産についての権利を第三者に主張できなくなるリスクがあります。
具体例をいくつか挙げてみます。
【事例1】
長男Aと次男Bが相続人となり、実家の土地と建物を相続しました。この実家にはAが住んでおり、この2人は「Aが住んでいるから当然Aが相続している」と考えていましたが、相続登記はせずに放置していました。そんなある日、Aのもとに突然、「不動産について、AとBで2分の1ずつ共有する旨の登記が完了しました」という手紙が法務局から届きます。後で調べると、どうやらBが多額の借金をしており、その債権者がBの財産を差し押さえようとして勝手に相続登記をしていたようです。
このような登記を、債権者代位登記と呼びます。相続人の債権者は、相続財産を法定相続分に基づいて名義変更し、差し押さえることができます。
【事例2】
妻Cは、夫が残したアパートを経営していました。しかし、古く小さなアパートだったこともあり、名義は亡夫のままにしていました。すると、夫が亡くなってしばらく後、アパートの入居者から「相続人が他にもいるかもしれない。誰が相続したかわからないから、賃料は払えない」と言われてしまいます。弁護士に相談した結果、どうやら夫の兄弟姉妹が相続人となるようで、相続登記に時間がかかってしまうそうです。賃料については、ひとまず供託(債権者不確知供託)をしてもらうことになりましたが、満額を受け取るには先に相続登記をしなければならないそうです。
このように、相続登記をしていないと、不動産の所有権がどの相続人にあるのかわからず、第三者との間でトラブルになってしまうことがあります。不動産を適切に管理するためにも、早めに名義変更を済ませておきましょう。
リスクその4:他の相続人と共同で不動産を管理しなければならない
不動産を含む相続財産は、遺産分割や名義変更といった相続手続きが終わるまでは、相続人が共有している状態にあります。
このような状態で不動産の管理(修繕やリフォーム、廃棄物の処理等)を行うとき、一部の行為は、相続人が1人ですることはできず、相続分の過半数をもつ相続人が協力して行わなければなりません。
このように、不動産に万一のことがあったとき、相続人間でスムーズに連携が取れないと管理行為ができなくなる恐れがあるので、名義変更を済ませ、管理者(=所有者)を明確にしておきましょう。
リスクその5:過料を支払わなければならない
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。
詳しくは次のセクションでお話しますが、この法改正により、相続登記をせずに放置していると10万円以下の過料が科される可能性があります。
「相続登記の義務化」とは?
次に、相続登記の義務化について解説します。
2024年(令和6年)4月1日に始まったこの制度により、不動産を相続によって取得した人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないというルールが新設されました(ただし、相続人が極めて多数にのぼる・遺産の範囲に争いがある・病気や貧困により登記ができないといった事情があれば免除されることもあります)。
「取得したことを知った日」とは、相続が始まった日や遺産分割協議がまとまった日など、具体的にその不動産を自分が相続すると知った日です。この日から3年以内に相続登記をせず、さらに法務局からの催促を放置してしまうと、10万円以下の過料が科される恐れがあります。
また、2024年(令和6年)4月1日以前に相続した不動産も、義務化の対象です。このような不動産についても、制度が始まってから3年以内(2027年(令和9年)3月31日まで)に相続登記をしなければ、同じく過料の対象となります。
ただし、「不動産を相続したことは知っているが、遺産分割に時間がかかっており3年以上かかりそう」といった場合には、相続登記の義務を果たすことができません。このような場合には、代わりに相続人申告登記をして、相続登記をする意思があることを示し、過料から逃れることもできます。
これまで相続登記は任意とされていましたが、相続登記をせずに放置された不動産が増えた結果、所有者がわからない土地(所有者不明土地)が全国的に増加し、都市開発などの各種不動産取引に支障を来していました。
また、地震などの災害が発生した際、倒壊した家を取り壊そうにも、現在の所有者がわからず、誰も手を付けられないという事態もありました。
相続登記が義務化された主な理由は、このような問題を解消するためです。相続登記を促すことで、すでに亡くなっている名義人のまま何十年も放置されることがなくなり、不動産の取引や管理が円滑になると期待されています。
相続登記の流れ
最後に、相続登記の流れを簡単にご説明します。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、あわせてご参照ください。
ステップ1:相続人と相続財産を確定させる
まず、相続人と相続財産を確定させます。
相続人は、戸籍で確認します。具体的に誰が相続人となるか、どのような戸籍が必要となるかは、以下の記事を参考にしてください。
不動産については、登記事項証明書や固定資産税の評価証明書で確認できます。また、被相続人の名寄帳を確認することで、その自治体にある被相続人所有の不動産がすべて確認できますので、財産に漏れが生じないよう、確認することをおすすめします。
ステップ2:必要があれば、相続人全員で話し合う
次に、誰が不動産を相続するかを決めます。
相続人が一人の場合や遺言がある場合には話し合いは不要ですが、そうでなければ相続人全員で話し合って決定しましょう。
ステップ3:遺産分割協議書を作成する
話し合いがまとまれば、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書の作り方については以下の記事にもまとめていますが、名義変更のために必要な重要書類であり、作り直すには相続人全員の協力が必要となりますので、ご心配であれば専門家に作成を依頼することをおすすめします。
ステップ4:登記に必要な書類を準備し、法務局に登記申請をする
最後に、相続登記の必要書類を準備し、法務局に登記申請をします。
必要となる主な書類は、以下のとおりです。
必要書類の具体的な内容については法務局のホームページでも案内されていますので、自分で手続きを進めたい方はぜひご確認ください。
まとめ
相続した家の名義変更を放置していると、売却や活用ができなくなるだけではなく、相続人が増えてしまったり、相続人間で協力をしなければならない場面が増えてしまったりと、将来世代に大きな負担を残すことになりかねません。
また、2024年からは相続登記が義務化され、名義変更を放置していると過料の対象にもなります。
トラブルや余計な手間を避け、資産を確実に守るためにも、相続が発生したらできるだけ早く名義変更を行うことが大切です。お悩みの方は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。