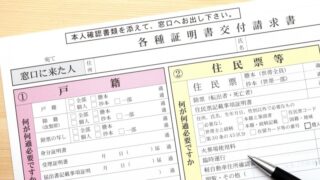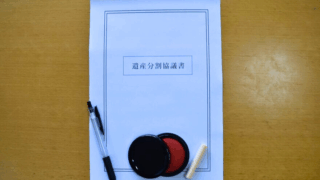相続手続きは、財産関係や相続関係が複雑であったり、相続人同士で話し合いができない状況であったりすると、数年単位の時間を要することがあります。そして近年は高齢化が進んでいることもあり、相続手続きを進めている最中に相続人が亡くなってしまうケースが増えています。
このように、相続人が亡くなって連鎖的に相続が発生することを、「数次相続」と呼びます。数次相続が起こると、亡くなった相続人の相続人が新たに手続きに関与しなければならず、当事者が増えることになります。
では、数次相続が発生した場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?
この記事では、数次相続の仕組みや、相続手続きの途中で相続人が亡くなった場合の対処法について、わかりやすく解説します。
相続人が亡くなったときに起きること(数次相続)
相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)の資産や負債を引き継ぐために、相続人が協力して手続きを進めていきます。この手続きには、銀行預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)のほか、遺産分割協議なども含まれます。
しかし、手続きが長引くうちに、相続人が亡くなってしまうことが起こり得ます。このような状態を数次相続と呼び、数次相続が起こると、亡くなった相続人の相続人が、元の相続手続きに新たに参加することになります。
具体例を挙げて考えてみましょう。
母親Aが死亡し、その子どもである長男B、長女Cの2人が相続人であるとします。Aの遺産分割協議をしようとしていたある日、Bが死亡し、その相続人はBの妻Dと子どもEでした。
このようなケースでは、Aの遺産分割協議は、C・D・Eで行うことになります。なお、Aの相続についての相続分は、Cが2分の1、D・Eが各4分の1ずつです。
さらに、DとEは、B名義の財産についても相続手続きをしなければなりません。
このように複数の相続手続きが発生するため、関係者の数が増え、手続きが複雑になってしまいます。
数次相続と似たような制度に、代襲相続があります。代襲相続とは、相続の開始前(=被相続人が亡くなる前)に、相続人となる予定だった推定相続人が死亡していたようなケースです。このような場合、相続人としての立場が下の世代に引き継がれます。
ただし、数次相続と代襲相続では結果が異なります。先ほどの例を使って考えてみましょう。
まず、長男Bが死亡し、その後に母親Aが死亡します。この場合、母親Aの相続については代襲相続が起こり、長女CとBの子どもEが相続人となります(Bの妻Dは、代襲相続の対象とはなりません)。
このように、死亡の順番によって数次相続と代襲相続が決まり、関係者も変わってきます。
手続きの流れ
では、数次相続が起きた場合には、具体的にどのような手続きが必要となるのでしょう? 基本的な流れは次のとおりです。
ステップ1:新たな相続人を確定する
まずは亡くなった相続人について戸籍を調査し、その相続人を特定します。
新たに集める戸籍として、必ず必要なものは「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」と「新たな相続人の戸籍謄抄本」であり、元の相続で集めてない場合には「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を揃える必要があります。
ステップ2:遺産分割協議が終わってない相続財産について、協議をする
次に、遺産分割が終わっていない相続財産について、新たな相続人を含めたすべての相続人で、遺産分割協議をします。
なお、既に遺産分割協議が終わっている相続財産については、基本的には再度の協議は不要です。ただし、遺産分割協議書には相続人が署名・捺印をし、印鑑証明書を添付しなければ、各種相続手続きが進められません。よって、たとえ既に遺産分割協議が終わっていたとしても、書面にまとめていなかったり、亡くなってしまった相続人の印鑑証明書が期限切れだったりすると、再度、新しい相続人を含めた遺産分割協議書を作成する必要が生じるため、注意が必要です。
新たに作成する遺産分割協議書については、
① 亡くなった順番
② 対象となる財産
③ 各相続人の立場(元の相続における相続人なのか、新たに相続人となった人なのか)
を明確にするようにしましょう。
そうすることで、名義変更などの手続きがスムーズに進みますし、後の争いの予防にも繋がります。
また、「元の相続での被相続人名義の財産」と「新たな相続での被相続人名義の財産」については、それぞれ別の遺産分割協議書を作成するようにしてください。
ステップ3:相続財産の名義変更を進める
最後に、名義変更が終わっていない預貯金や不動産について、名義変更の手続きを進めていきます。
名義変更の際にはステップ1で新しく集めた戸籍やステップ2で作成した遺産分割協議書が必要となるので、提出する機関に必要書類を確認しながら準備しましょう。
不動産を新しく相続人となった人に相続させることになった場合、状況に応じて
① 一度亡くなった相続人の名義に変えてから新しい相続人の名義にする必要がある
② いきなり新しい相続人の名義にできる
の2パターンがあります。
②にするとコストが抑えられ手続きが簡略化できますが、②にするには、省略する相続人が1人である必要があります。
例えば、父Aが亡くなり、兄Bと弟Cが相続人となったが、途中でBが亡くなった場合に、A名義の不動産を……
① Bの妻Dと弟Cが2分の1ずつ相続する
→ 中間省略登記不可
② Bの妻Dのみが相続する
→ 中間省略登記可能(省略する相続人がBのみなので)
※ ただし、相続税がかかる場合には、一度B名義を経由した方が節税として有利な場合もあります。
※ 中間相続登記について、後日詳しい記事を公開予定です。
まとめ
相続手続きの最中に相続人が亡くなると、数次相続が発生し、相続人の範囲が広がります。その結果、相続手続きが中断したり、遺産分割協議に関わる人数が増えたりと、手続きが複雑になる可能性が高くなります。
ただでさえ精神的に負担がかかる慣れない手続きの最中にこのような事態になると、つらく感じる方も多いでしょう。そんな負担を少しでも減らせるよう、専門家に依頼して煩雑な手続きを免れることもご検討ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。