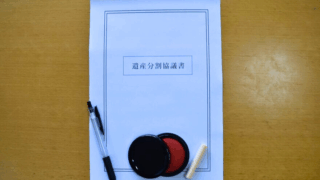相続の場面では、亡くなった方(被相続人)を長年介護していた相続人や、家業を長年手伝っていた相続人などが、「自分が多く財産をもらえないと不公平だ」と感じることがあります。
このような状況を調整する制度が寄与分という考え方です。寄与分については民法で定められており、介護や労働などにより被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に多く財産を分配することで、不公平感をなくす仕組みになっています。
ただし、寄与分が認められるには様々な要件があり、その性質から、相続争いといったトラブルに繋がってしまうことも少なくありません。
この記事では、寄与分の基本や認められるための要件、主張のポイントをわかりやすく解説します。
寄与分とは
寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合に、その貢献度合いを考慮して相続分を増やす制度です。寄与分が認められることで、各相続人の実際の貢献度を反映した公平な遺産の分配が可能となることが期待されます。
寄与分は、相続人全員での遺産分割協議の際に考慮されます。しかし、反対する人がいる場合や、具体的な金額について意見がまとまらない場合には、裁判所での遺産分割調停や審判で決められることになります。
そのため、寄与分を主張したい相続人は、あらかじめ「特別な貢献」を証明するための客観的な資料を集めておくことが大切です(どのような証拠が必要かは後述します)。
民法904条の2第3項により、遺贈は寄与分よりも優先されると規定されています。これは、客観的な事実よりも、被相続人が遺した遺言の内容を優先するためのルールです。
したがって、遺産がすべて第三者に遺贈されてしまった場合には、寄与分を主張することはできません。ただし、遺留分を主張できる可能性はあります。
寄与分の要件
寄与分が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
要件その1:法定相続人であること
寄与分を主張できるのは、民法で定められた相続人だけです。たとえ被相続人を長年介護していたなどの特別な事情があっても、相続人でなければ寄与分を主張することはできません。
そのため、寄与分を主張したい場合には、自分が相続人にあたるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
相続人となるのは配偶者や子どものほか、子どもがいない場合には親、さらに親もいない場合には兄弟姉妹といった血縁者です。
相続人ではない内縁関係の相手や子どもの配偶者などは、寄与分を主張することができません。このような方々に遺産を残したいときは、遺言を残す必要があります。
寄与分とよく似た制度に特別寄与料がありますが、これは相続人でなくとも親族であれば請求ができるものであり、そのほかの細かい要件も異なっています。
特別寄与料については、後日記事を更新します。
要件その2:被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
寄与分が認められるには、「被相続人の財産を維持または増加させた」という事実が必要です。
民法の条文では「事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」によって財産を維持・増加させたことと規定されていますが、具体的には以下のような行為(=寄与行為)をした人に寄与分が認められやすいというのが実務上の考え方です。
要件その3:通常の範囲を超えた貢献度合いであること
寄与分が認められるには、要件その2で述べた寄与行為について、通常の血縁者に期待される程度を超えた行為をして、財産の増加に貢献していなければなりません。
「通常の血縁者に期待される程度」は人によって差があるでしょうが、例えば家事従事型であれば「時折り職場の掃除をしていた」程度では認められませんし、医療看護型であれば「怪我のリハビリのため1年間移動を手伝っていた」程度では認められません。
とはいえどの程度の貢献が必要かどうかは一概に決まるものではなく、各事案の状況や社会通念、関係者の価値観等によって変わります。相続人間の話し合いで決まらなければ、裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判で決めることになります。
要件その4:無償かつ継続的な行為であったこと
最後に、寄与分が認められるには、要件その2で述べた寄与行為を無償かつ継続して行っていなければなりません。
例えば、家事従事型なら給料を受け取っていれば寄与行為になりませんし、医療看護型なら数週間の介護は寄与行為になりません(一般的に、3年以上の介護行為があれば認められやすいそうです)。
ただし、この基準も一概に決まるものではなく、たとえ給料を受け取っていたとしても、それが著しく少額であれば無償とみなされることもあります。
このように寄与分は、相続人が、無償かつ継続的な行為を行って被相続人の財産を増加・維持し、その行為が通常期待される範囲を超えていたことが要件となるのです。
寄与分の請求方法
それでは、寄与分を請求したい相続人は具体的にどのような手続きをとればよいのでしょうか。
まずは遺産分割協議で話し合います。遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って被相続人の財産や負債の分け方を決めることです。この協議のなかで「こういった貢献をしていたから多くもらいたい」という意見を出して他の相続人が納得すれば、そこで寄与分の問題は解決します。
なお、相続人全員が合意していれば、先述の要件を満たさないような行為であっても取り分を多くすることもできます。遺産分割協議であれば、要件はそこまで気にしなくてよいということです。
次に、相続人全員で話がまとまらなければ、裁判手続きを利用して遺産の分割をすることになります。
裁判手続きは、調停と審判があり、前者では裁判所が相続人間の話し合いをサポートし、後者では裁判所が客観的な資料をもとに寄与分の有無やその額を決定します。
この裁判手続きの段階では、先述の要件が重視されます。客観的な資料を残し、要件を満たしていることを主張できるよう、準備が必要です。
どのような証拠が必要?
寄与分の主張をするには客観的な資料を残しておくことが大切ですが、そんな証拠の具体例は以下のとおりです。
このように、事情を知らない第三者が見て寄与行為があったことがわかるような資料が必要です。
寄与分の計算方法
寄与分の計算方法は特に決まった基準があるわけではなく、個々の事情や寄与行為の程度、過去の裁判例などから総合的に判断されます。
ただし、認められる寄与分の上限は遺産総額です。また、裁判となると、他の相続人との兼ね合いも考慮されるため、寄与行為による貢献度合いがいくら高くとも、すべての遺産を相続できると認められることは少ないです。
このように、決まった基準が存在しない寄与分の相場ですが、目安になる金額も存在します。例えば、家事従事型であれば「本来受け取るはずの給料」、医療看護型であれば「本来介護ヘルパー等へ支払うはずだった金額」、金銭等出資型であれば「被相続人にもたらした金銭的利益」などです。
裁判所では、過去の裁判例と同様の方法でこのような金額を算出し、個別の事情に当てはめて最終的な決定がなされます。
注意点
最後に、寄与分についていくつか注意点を挙げていきます。
注意点その1:認められるのが難しい
寄与分は、他の相続人の相続分を減らしたうえで認められるものです。その性質上、簡単には認められず、先述のとおり様々な要件が設けられています。
相続人全員が合意さえすれば要件は問題にはなりませんが、裁判となると要件を満たしているかを厳格に審査されるため、寄与分を認めてもらうにはそれ相応の証拠が必要です。
寄与分の要件は法律で厳密に定められており、主張する際にはその他様々な注意点にも配慮しなければなりません。また、相続開始時と遺産分割時の両方の財産評価を考慮する必要があり、評価額がわからないと話合いが進まず、結果として遺産分割全体に遅れが生じてしまうこともあるでしょう。
相続人全員が「このくらい貢献してくれたんだから多く貰うのは当然だ」と考えてくれるようなケースであれば問題ありませんが、少しでも話が食い違うようなことがあれば、弁護士へ相談することをおすすめします。
注意点その2:関係悪化等に繋がるリスクがある
寄与行為をしていた人が寄与分を主張するのは当然の権利ではありますが、お金や感情の問題でもあるため、話合いを通じて相続人間の関係性が悪化するリスクもあります。
また、法律の観点では寄与行為を主張するための十分な証拠を残しておくべきですが、他の相続人からすると「お金のためにこんなに細かく証拠を残していたのか」と感じてしまうこともあるかもしれません。
このように、寄与分は揉め事に繋がりやすい傾向にあるので、できれば被相続人の生前に遺言を書いてもらうなど、事前の対策をしておきたいものです。
注意点その3:期間の制限がある
2023年(令和5年)4月の民法改正により、遺産分割ができる期間が被相続人の死亡から10年と定められました。10年を経過すると、法定相続分どおりに遺産を分割したとして処理され、寄与分の主張は原則として認められなくなります。
とはいえ事実上、10年が経過する前であっても、時間が経ってしまうと証拠を集めるのが難しくなり、当時の記憶も薄れてしまいます。寄与分を主張するには、できるだけ迅速に行動に移ることが大切です。
注意点その4:遺産分割のやり直しで税金がかかることも
一度遺産分割が終わった後に寄与分を考慮した遺産分割を再度やり直すと、贈与税や譲渡所得税がかかるおそれがあります。また、相続税を納めていた場合には、再度相続税を納め直す必要も生じるでしょう。
このように、遺産分割をやり直すと課税リスクが発生します。できるだけ一度目の遺産分割で寄与分を主張するように注意しましょう。
まとめ
寄与分は、相続人の中で特に財産の維持や増加に貢献した人を公平に評価するための制度です。しかしその成立には様々な要件があり、実際に主張するには、客観的な証拠を集めることが欠かせません。
相続は感情的な対立を生みやすく、寄与分の主張もトラブルの火種になりがちです。公平な解決のためには、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
また、相続開始前であれば、被相続人となる方に遺言を書いてもらうなどの対策を検討しましょう。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。