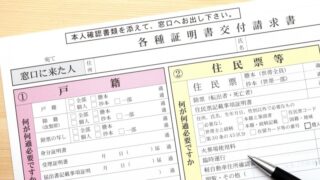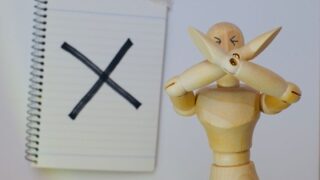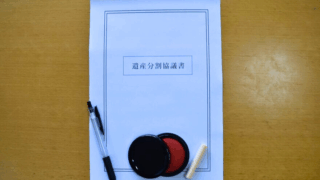人が亡くなって相続が発生すると、相続人(または遺言執行者)は、その財産や負債を引き継ぐための相続手続きを行うことになります。
相続手続きにおいてまず初めに必要となるのは、相続人と相続財産の確認です。誰が相続する権利をもっているのか、そして何を相続するのかを確定させなければ、財産を分けようにも、話し合いを始めることもできません。
相続人については戸籍を調査すれば漏れなく確認することができますが、問題となるのは相続財産の確認です。財産は、不動産や預貯金、株式等の有価証券のほか、年金、保険契約、自動車、事業用資産、そして近年はオンライン上にのみ存在するデジタル遺産など、多岐にわたります。また、このようなプラスの財産のみならず、ローンや保証債務などの負債についても漏れなく調査しなければなりません。
故人が生前に財産の一覧表を残していれば調査はスムーズに進みますが、実際にはそうでないことが多く、相続人がいちから財産を調べ上げなければならないケースも多くあります。そのような場面で相続財産の調査が不十分だと、相続人同士のトラブルや、遺産分割・相続税の申告・相続放棄などの重要な手続きの遅れなど、取り返しのつかない事態にも繋がりかねません。
この記事では、被相続人の財産調査の方法や、財産調査の際に気を付けたいことなどをわかりやすく解説していきます。
相続時における財産調査のおおまかな流れ
まずは、財産調査のおおまかな流れを確認しましょう。
- 財産調査の下準備を行う
→ 葬儀が終わりひと段落したら、年金の停止や各種支払いの停止、公共料金等の引き落とし口座の変更、クレジットカードやスマートフォンなどの各種サービスの解約等の、日常の収入・支出に関する手続きを進めていきます。
相続財産の調査を始めると、銀行口座が凍結されます。よって、このような手続きを事前に終わらせておくことで、引き落としができなかった等の行き違いがなくなり、後の事務処理の負担が軽減できます。 - 被相続人の自宅で遺品を調査する
→ 次に、相続財産調査の取り掛かりとして、被相続人が住んでいた自宅で遺品の調査をします。これらの情報を手がかりとして、相続財産の調査を進めていきます。
【探す物の例】
不動産の権利証、売買契約書、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、株式等有価証券の残高報告書や配当通知などの証券会社から届いたもの、年金証書、保険証券、確定申告書類、固定資産税や住民税など各種税金の通知、消費者金融のカード、契約書、保証契約書
【探す場所の例】
カバンや財布などの身の回りの貴重品、タンス・棚・引出し・押し入れ・床下収納などの各種収納、郵便受け、パソコンやスマートフォンなどの電子機器、その他金庫や枕の下などの貴重品を入れそうな場所 - 見つかった手がかりを元に、各機関に照会する
→ 2で見つかった手がかりを元に、各機関に照会していきます。照会には相続人であることを示すための戸籍が必要となることがほとんどですので、この段階までに戸籍の収集を終わらせておきましょう。
照会先は、不動産であれば法務局や役所、預貯金であれば銀行など多岐にわたりますので、後記「各種財産の調査方法」で詳しく解説します。 - 財産目録を作成する
→ 最後に、各機関から集めた情報をもとに、財産の一覧表(財産目録)を作ります。財産目録とは、各財産を種類ごとにまとめたものであり、これがあれば相続人間での話し合い(遺産分割協議)が進めやすくなります。
作成は必須ではありませんが、財産の種類が多い場合や関係者が多い場合には、作成をおすすめします。
財産調査を確実に行うべき理由
では、細かい話の前に、そもそもどうして相続財産調査をしっかりと行わなければならないのか、その理由をまとめておきます。
相続財産調査を確実に行うべき理由は、大きくわけて4つあります。
理由1:相続放棄や限定承認をするか否かを判断するため
被相続人の負債が多かったり、どれだけ負債があるかわからなかったりする場合の選択肢として、相続放棄や限定承認があります。相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになりますし、限定承認をすれば被相続人の財産の額を超える負債の返済義務はなくなりますが、どちらも被相続人の死亡を知った日から3か月以内に裁判所に申述しなければ利用できません。つまり、被相続人が亡くなってから3か月以内にその財産調査を終了し、負債がどのくらいあるかを把握しなければならないのです。
理由2:適切な遺産分割を行うため
被相続人の財産の分け方は、遺言がない限り、相続人同士で話し合う遺産分割協議によって決まります。この遺産分割協議の前提として、どのような財産・負債がいくらあるかが確定している必要があります。「あとから財産が見つかって遺産分割をやり直す羽目になった」「財産額が曖昧なまま遺産分割をしてしまい、裁判沙汰になった」といったトラブルを防ぐためにも、先に財産の詳細を把握しなければならないのです。
理由3:適切な相続税申告を行うため
相続財産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、相続税を申告しなければなりません。この相続税の申告期限は相続開始後から10か月であり、それまでに相続財産の調査を終え、遺産分割方法を確定させ、相続税の申告書を完成させなければならないのです(ただし、遺産分割が終わらない場合に申告期限を伸長する制度もあります)。
また、申告を終えた後に新たな財産が発覚した場合、相続税の修正申告が必要となり、延滞税等のペナルティが課されることもあります。このような事態を避けるためにも、相続税の申告前にきちんと財産調査を終える必要があります。
理由4:正しく名義変更を行い、適切に財産を管理するため
財産の所有者を明確にするために、遺産を相続した人は、その遺産の名義を被相続人から自身に変更する必要があります。預貯金であれば自分の口座への振込み、不動産・株式・自動車等の名義変更、保険金の受取り等、手続きは多岐にわたりますが、こういった手続きを放置してしまうと、後から所有権争いになったり、税務上のリスクがあったりと、不都合が生じます。また、放置したまま長期間が経過してしまうと、手続きに必要な資料が集めづらくなってしまうなど、さらに手続きが煩雑になる恐れもあります。
さらに、近年は不動産の相続登記が義務化されるなど、名義変更を放置してしまうと過料に科されることも。しっかりと名義変更の手続きを終えるためにも、相続財産の調査を適切に行うことが重要です。
各種財産の調査方法
それでは、各種財産について、財産の有無やその詳細を調査する方法を細かくみていきましょう。
不動産(土地・家屋)
土地や家屋といった不動産は、法務局で管理されているほか、役所の固定資産税課でも把握しています。
法務局では、各土地や家屋について登記記録を作成し、地番・家屋番号を付して管理しています。この登記記録を見れば、「不動産の所有者は誰か」「大きさはどのくらいか」「抵当権や質権などの担保がついているか」を確認することができます。
※ 2026年(令和8年)2月2日から全国の不動産を一括で確認するための新しい制度が始まり、法務局での不動産の検索がより便利になります。
さらに、法務局でも管理できていない建物(未登記建物)が存在することもあります。そのような建物を把握しているのが役所の固定資産税課です。登記されていない建物に対しても、固定資産税は課されていることがほとんどです。よって、役所に照会することで、法務局ではわからなかった不動産の存在が判明することがあります。
このような特徴から、不動産は以下の方法で調査すると効率的です。
- 不動産の登記済権利証や固定資産税納税通知書からわかる所在地や地番、家屋番号をもとに、登記記録を閲覧する(または、登記事項証明書を取得する)。
→ 登記記録・登記事項証明書は、全国の法務局で取得できるほか、オンラインでも取得できます。
→ 地番や家屋番号が分からない場合は、その不動産を管轄する法務局に電話をして不動産の住所を伝えると教えてくれます。 - 不動産がある市区町村役場から、固定資産税の評価証明書と名寄帳を取得する。
→ 固定資産税の評価証明書には、役所が把握している不動産が一覧化されています。ただし、固定資産税が課されていないような私道等は記載されていない場合があります。そのような場合には名寄帳を確認することで、すべての不動産を確認することができます。 - 不動産を賃貸している場合や土地に地上権が設定されている場合には、その賃貸契約等の基礎となる契約書を確認する。
特に未登記建物や、固定資産税が課税されていない私道は見落としやすいため、注意しましょう。
遺産分割協議をする際には、不動産の価値が問題になることがあるでしょう。不動産には以下のようないくつかの評価基準があるので、このような価格を参考に遺産分割をしましょう。
※ 遺産分割は、相続人全員の合意さえあれば、原則としてどのような分け方をしても構いません。ただし、不動産の評価額は相続人の立場や価値観によって大きく左右されることがあるので、争いに繋がりそうな場合は専門家の介入をおすすめします。
- 公示価格:国土交通省が公表する毎年1月1日時点の全国各地の基準地の価格
- 固定資産税評価額:市町村が定める毎年1月1日時点の土地の価格。固定資産税の課税基準であり、公示価格のおよそ7割となる。
- 路線価:国税庁が公表する毎年7月1日時点の土地の価格。相続税の課税基準であり、公示価格のおよそ8割となる。
- 実勢価格:実際にその不動産の売買取引が成立した価格
預貯金
預貯金については、通帳やキャッシュカードから判明した取引銀行に照会して、解約手続きを進めます。
照会する際は、支店に直接電話等で連絡するほか、三井住友銀行やりそな銀行ではオンラインによる相続手続きも受け付けています。銀行に連絡すると口座が凍結され、入出金が停止されるので、引き落としが残っている場合などには注意しましょう。
銀行に連絡した後の流れは銀行によっても異なりますが、大まかには① 戸籍謄本等の相続人を確認できる書類や相続人の印鑑証明書を提出する、② 相続手続きの申込書(相続届等)を提出する、③ 遺言や遺産分割で決められた支払先に預貯金が振り込まれる、といった流れになります。各銀行の手続きの流れに従い、必要な書類を準備しましょう。
なお、近年はネット銀行も主流になっていますが、ネット銀行は通帳がなく、口座が見つけられないケースもあるので、被相続人のスマートフォンにネット銀行系のアプリが入っていないかなどを確かめましょう。
また、相続税の申告が必要となる場合、死亡時の残高証明書が必要となるため、解約の手続きと同時に取得しておきましょう。さらに、過去5年間程度の取引履歴を確認しておくことで、「多額の引出し・贈与・売買がないか」「判明していない他口座に振り替えていないか」等を知ることができます。
故人の預貯金を調べようにも、どの銀行に口座があるのかわからないこともあるでしょう。
マイナンバーが登場したことで、すべての銀行を一括で調査する方法もできたにはできたのですが、2025年時点で、まだ普及しているとはいえず、どの銀行に口座があるのかを一括で照会することはできません。よって、被相続人の通帳やキャッシュカードから取引銀行を特定していく作業が必要です。
また、同じ銀行の他の支店に口座がないかを確認してもらう制度もあります(銀行によって「全店照会」や「名寄せ」といいます)。このような制度を利用して、預金の調査を進めていきましょう。
有価証券(株式、投資信託など)
株式や投資信託といった有価証券は、証券会社で保管されています。よって、有価証券の相続手続きは、各証券会社に連絡して進めることになり、そのためにも、どの証券会社に口座があるかを調べる必要があります。
その調査の基本的な方法は、自宅にある証券会社から届いた書類や確定申告書類を確認することです。また、通帳の入出金記録に証券会社の名前がないかを調べるのも有効な方法です。特に郵便物については他界後しばらく経ってから新たに届くことも多いので、定期的に確認するようにしましょう。
また、証券口座については、上場株式の所有者を一括で管理している「証券保管振替機構(ほふり)」に開示請求をすることで照会することができます。手数料はかかりますが、漏れなく相続するためにも、被相続人が有価証券をもっている場合には開示請求をしておくと安心でしょう。ただし、未上場株式については開示請求をしても捕捉することはできません。自宅にある株券や郵便物等から未上場株式があると疑われる場合には、その株式を発行する会社に個別に問い合わせましょう。
保険金(生命保険、未払いの医療保険や年金など)
保険金が相続財産として扱われるか否かは、その契約形態によって変わります。
まず、相続人を受取人とした生命保険金は、原則として相続財産に含まれません。しかし、相続税申告においては「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。
次に、被相続人が生前手術や入院をしていたことによる医療保険金などは、相続財産にあたります。
保険契約や年金の有無については、保険証券や年金証書、保険会社から届いた郵便物のほか、通帳の取引履歴やクレジットカードの利用履歴等から判明することがあります。このような手がかりを元に、保険会社等に問い合わせましょう。
また、被相続人が会社員だった場合、会社を通じて保険に加入していることもあるので、手続きの流れについて会社に問い合わせてみましょう。
財産価値のある動産(自動車、貴金属、美術品など)
財産価値のある動産(自動車、貴金属、美術品など)も、預貯金や不動産と同様、相続の対象となります。特に自動車については所有者が登録されており、陸運局での名義変更をしなければ処分できませんので、注意が必要です。
その他の動産については名義変更等の手続きがあるわけではありませんが、相続においてはその価値を把握しておかなければ遺産分割の話合いに支障が出る場合があります。また、相続税の申告においては、動産も課税の対象となるため、専門家に査定を依頼する等の方法で適切に評価しなければなりません。
事業用資産
被相続人が個人事業主だった場合、事業用資産も通常の財産と同様に相続の対象となります。個人事業主が亡くなった場合の相続手続きの主な注意点は以下のとおりです。
デジタル資産
デジタル資産とは、電子マネーや各種ポイント、暗号資産、デジタル上の著作物など、デジタル上にしか存在しない資産のことです(ネット銀行・ネット証券も含まれることがあります)。
このような資産であっても、相続手続きの流れは他の資産と特段変わりません。ただし、現物がある他の資産と違って、資産自体が発見しづらいという特徴があります。また、管理している会社が外国にある場合は、解約に時間がかかることもあるので、このような資産については極力本人の生前に整理しておきたいところです。
さらに、有料サブスクリプションサービスなど、月額・年額で支払いが自動的に続くサービスも、相続人が解約しなければなりません。このような利用料についても、支払履歴が見つかり次第対応するようにしましょう。
債務(借金、ローン、保証債務など)
被相続人の債務は、調査が漏れてしまうと想定外の借金を負ってしまいかねない重要なものです。また、心理的な面から、本人が誰にも話していないことも多いので、確実に調査をするようにしましょう。
被相続人の債務とその手がかりとして、以下のようなものが考えられます。
このように、確認の方法はいくつかありますが、実際には相手方から請求や督促がこない限りわからない債務も多いです。知らない借金についていきなり連絡がきたときは、慌てて支払わず、落ち着いて詳細を確認するようにしましょう。
さらに、念のため、各信用情報機関(JICC、CIC、KSC)へ信用情報の開示請求をしましょう。信用情報機関には、過去5年間の借入れの履歴などの債務に関する情報が登録されています。相続人であれば戸籍や本人確認書類を提出することで開示請求ができますので、しておくと安心です。
ただし、どの信用情報機関にも登録されない債務(保証債務、個人間の借金、公共料金や税金の滞納)もあります。信用情報機関への問い合わせでおおむねの債務は確認できますが、遺品の捜索もあわせて行う必要があるのです。
まとめ
相続財産調査は、相続手続きの前提となる作業でありながら、非常に手間のかかる作業でもあります。特に故人が一人暮らしだった場合などには、どこにどのような財産があるのかわからず、何から手をつければよいかわからないといったケースもあるでしょう。
ぜひ今回紹介した財産の種類を参考に、相続財産の整理をはじめてみてください。
また、ひろはた司法書士事務所では、相続財産の調査や解約・名義変更の手続きの代行を取り扱っております。手続きの時間が取れない方や手続きの進め方にご不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。