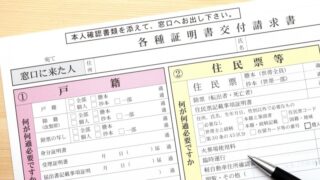亡くなった人が遺した遺言書を見つけたら、どうすればよいのでしょう?
実は、遺言書があったからといってすぐに口座の解約や不動産の名義変更といった相続に関する手続きができるわけではありません。見つけた遺言書が一定の形式のものであれば、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければならないのです。
この検認は、遺言書の形式が法律的に正しいかどうかを確認する手続きです。また、封がされている遺言書については検認の場で開封することとなり、その内容を担保することもできます。
今回は、そんな遺言書の検認について、概要や手続きの流れ、どのような場合に必要なのかをわかりやすく解説します。
遺言書の検認とは?
概要・目的
検認とは、亡くなった方(被相続人)が残した手書きの遺言(=自筆証書遺言または秘密証書遺言)の形式的な内容を確認するために、家庭裁判所で行う手続きのことをいいます。
家庭裁判所は遺言書の形式が民法に定められたルールに従っているかを確認した後、相続人全員に通知を発し、検認の期日に集まるよう命じます。そして検認の期日には、相続人立会いのもと、遺言の内容が確認・記録されます。この手続きにより、「遺言が形式上有効であること」および「検認の期日における遺言書の内容」が確認され、遺言書に家庭裁判所のはんこが押された証明書が付されます。
この手続きにより遺言書の形式的な審査が行われるだけでなく、相続人に遺言書の存在が知らされ、さらには検認の期日における遺言書の内容が裁判所で記録されるため、遺言書の偽造や変造を防ぐこともできるのです。
そして、手書きの遺言書は、法務局で保管されているものを除き、この検認の手続きを終えなければ銀行の預金解約や不動産の名義変更に使うことができません。相続手続きをスムーズに進めるためにも、遺言がある場合は、速やかに検認の手続きを進めましょう。
検認が必要となる遺言書の種類
検認は、すべての種類の遺言書に必要なわけではありません。ざっくりと分類すると、「法務局や公証役場で確認されているかどうか」が判断基準となり、確認されていれば検認不要・確認されていなければ要検認となります。
具体的には、以下のように分類されます。
自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文が手書きで書かれた遺言です(法務局での保管については、下記「検認が不要になる『自筆証書遺言書保管制度』」をご覧ください)。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言であり、遺言者の手元に謄本があるほか、遺言書の原本が公証役場で保管されている公的な遺言です。
秘密証書遺言とは、封をして遺言者の手元で保管されている遺言であり、その存在が公証役場に登録されている遺言です。
以上のような遺言の形式のうち、すでに遺言書の形式が確認されている「法務局で保管されている自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は検認が不要です。
検認の注意点
検認には、いくつか知っておきたい注意点があります。
注意点1:検認を怠ると過料に科されるリスクがある
遺言書の検認については民法第1004条・第1005条に定められており、遺言書の保管者または遺言を発見した相続人は、遺言者が亡くなった後、遅滞なく遺言書の検認を受けなければ、5万円以下の過料に科されます。また、封がされている遺言書を勝手に開封した場合も、同様に、5万円以下の過料に科されるとも規定されています。
(遺言書の検認)
民法 | e-Gov 法令検索
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
このように、手書きの遺言書を見つけたら、開封せずにそのまま家庭裁判所に提出し、検認を受けなければならないのです。ただ、仮に誤って開封してしまったとしても、必ず罰金が科されるというわけではありませんし、遺言が無効になるわけでもありません。どのような状態でも、ひとまず検認を受けるようにしましょう。
注意点2:相続手続きが遅れ、相続放棄ができなくなる
遺言がある場合の相続手続きは、一般的に、「相続人の調査をする→遺言の検認を申し立てる→資産や負債を確認する→相続するか否かを判断する(相続放棄の判断)→資産の名義変更等を進める」という流れで行います。相続放棄は被相続人の死亡を知った後3か月以内にしなければなりませんが、遺言の検認が遅れてしまうと、相続放棄の判断が遅れてしまい、相続放棄ができなくなるリスクがあるのです。
また、遺言の保管者がなかなか検認をしないことで、他の相続人から「遺産を隠しているのではないか?」「遺言書を隠したいのではないか?」と疑われるリスクもありますし、相続手続きが遅れることにより相続財産が適切に管理されず、トラブルにつながることもあります。
このような様々なリスクを避けるためにも、遺言の検認は速やかに行う必要があるのです。
注意点3:検認は遺言の形式を審査するものであり、遺言の内容が有効とは限らない
遺言の検認は、あくまで「遺言の存在を相続人に知らせ、遺言が形式的に正しいかを審査し、遺言の偽造や変造を防ぐ」ことを目的とする手続きです。よって、検認が無事に終わったとしても、遺言書が法律的に有効であるとは限りません。内容の実現が不可能であったり、内容が法的に誤っていたり、もしくは遺言者が認知症のため遺言を書く法的能力がないと判断されたりといった事情で、遺言が無効となることもあるのです。
遺言が有効か否かを確認するには、検認の手続きの後、別途話し合いをするほか、話し合いがまとまらなければ、調停や訴訟といった裁判手続きをすることになります。
遺言書が2通ある場合には、ひとまずどちらも検認を受けて、その後、遺言の有効性を判断することになります。
遺言書を隠したり破棄したりすると、最悪の場合、相続する権利を失ってしまう恐れもあります。どちらも適切に検認を経て、専門家に相談するなどして遺言書の効力を判断するようにしましょう。
注意点4:検認を申し立てた人(申立人)は、一度は家庭裁判所に行かなければならない
家庭裁判所に遺言の検認を申し立てると、実際に家庭裁判所に集まって遺言の形状を確認する日(検認の期日)が設定されます。この期日には、申立人を含む相続人全員が呼び出されますが、このうち申立人は欠席することができず、必ず家庭裁判所に行かなければなりません。なぜなら、この期日に申立人が遺言の原本を持参するからです。遺言の原本がなければ検認の目的を果たせませんので、このような取扱いになっています。
とはいえ、期日は一方的に通知されるものではなく、事前に申立人と家庭裁判所で日程調整をすることができます。この期日に申立人が欠席してしまうと、再度期日を設定するところからやり直すことになりますので、必ず出席するようにしましょう。
検認の期日には申立人以外の相続人も出席することができますが、他の相続人は日程調整をしたわけではないので、出席したくともできないことがあるでしょう。
このような場合であっても、特段相続人が不利益を被ることはありません。
遺言の内容や検認で確認されたことを知りたい場合は、後日、家庭裁判所に「検認調書」の発行を請求することで確かめることができます。
検認の申立ての流れ
それでは、実際に遺言の検認をするには、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
遺言の検認を家庭裁判所に申し立てる際の具体的な流れは、以下のとおりです。
ステップ1:管轄の家庭裁判所を確認し、必要書類を準備する
まずは、どの家庭裁判所に検認の申立てをするかを確認し、必要な書類を準備します。
検認を申し立てる裁判所は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。つまり、亡くなった人が住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。どこが管轄しているかについては、家庭裁判所のホームページで確認しましょう。
また、申立てに必要な書類は、以下のとおりです(こちらも家庭裁判所のホームページで公開されています)。
特に戸籍の収集については、相続人が多い場合には数か月単位の時間がかかることもあるため、注意が必要です。どのような戸籍を集めればよいかについては、以下の記事を参考にしてください。
ステップ2:申立書を提出する
書類が集まったら、管轄の家庭裁判所に申立書を提出します。窓口で提出するほか、郵送での提出も可能です。
申立てをすると、後日裁判所から検認の期日を決めるための日程調整の連絡が入ります。期日が決まると裁判所から相続人全員に対し期日の案内が届きますので、その日に出席するようにしましょう。
※ 連絡を受けただけの相続人は欠席しても構いませんが、日程調整をした申立人は必ず出席する必要があるので注意してください。
申立てから検認の期日までには、裁判所の混雑具合にもよりますが、1~2か月程度の時間を要します。
ステップ3:検認の期日に出席する
検認では、申立人と出席した相続人の立合いのもと、裁判官による遺言書の確認が行われます。
流れとしてはまず裁判官が遺言書を開封し、その形状や筆跡、押印の有無などを確認し、その内容を検認調書として記録します。
所要時間は早ければ10分ほどで、無事に終了すれば遺言書の原本に「検認済証明書」がつけられ、裁判所のはんこで契印されます。
ステップ4:遺言の内容に従って相続手続きを進める
検認済証明書がつけられた遺言書は、各種相続手続きに使えるようになります。銀行預金の解約や不動産の名義変更など、各種手続きを進めていきましょう。
検認が不要になる「自筆証書遺言書保管制度」
これまで、自筆証書遺言であれば必ず検認が必要でした。しかし、2020年(令和2年)7月以降、法務局で遺言書を保管できる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
この制度を利用すれば、事前に法務局で遺言書の形式を審査してくれるため、検認の手続きが不要になります。また、遺言書の紛失や偽造を防ぐことができ、相続が始まったことを相続人に通知することもできるので、手書きの遺言を残したい方はぜひ活用してください。
まとめ
遺言の検認は、手書きの遺言書が自宅で見つかった場合に必須の手続きです。この手続きは遺言書の存在を相続人に知らせ、その内容を確認し、遺言書の形式に不備がないことを確かめるためのものです。
具体的な相続手続きの前に必ず行わなければなりませんが、あくまで形式面の確認であり、遺言書の法律的な有効性を判断するものではないことに注意が必要です。
また、検認をせずに遺言書を隠匿したり破棄したりした場合、過料を科されるおそれもあります。相続手続きを安全かつ速やかに進めるためにも、遺言書を見つけたら速やかに検認の手続きを行いましょう。ご不明点があれば、司法書士等の専門家に相談してください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。