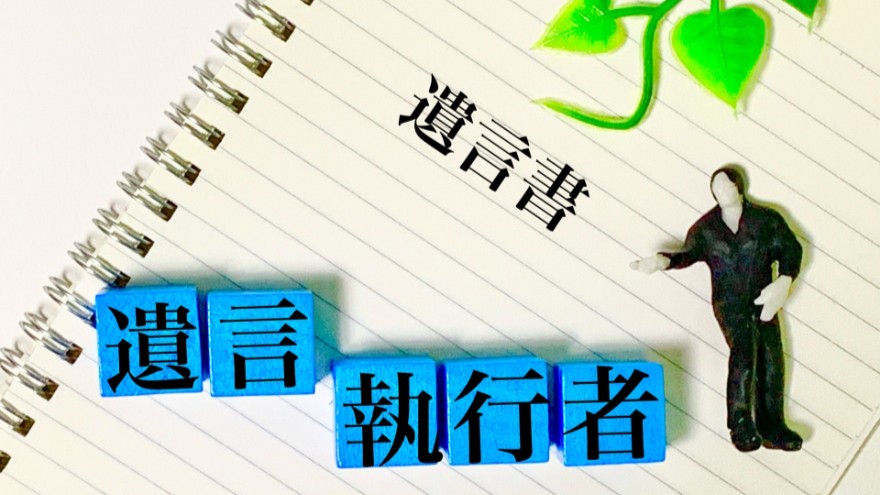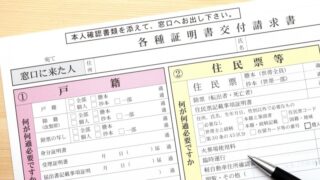遺言を残すとき、その遺言の内容に従って手続きを進める担当者として遺言執行者を指定することができます。遺言執行者が代表して相続手続きを進めることで、手続きがスムーズに進むだけではなく、相続人の負担が軽減されるというメリットもあるので、遺言を書くときにはあわせて遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
しかし、遺言執行者の選任には一定のルールがあります。また、「誰を選べばいい?」「自分の場合は必要なの?」「具体的にどういう仕事をする人なの?」といった疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺言執行者の基本的な役割や指定の方法、選ぶ際の注意点について、わかりやすく解説します。
遺言執行者とは? どのような場合に必要か
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言に書かれた内容を実現するため、相続財産の管理や解約、分配、名義変更などの手続きを行う人です。
通常であれば相続手続きは相続人が共同して行わなければなりませんが、遺言執行者がいる場合には、銀行預金の解約や相続登記といった手続きは、原則としてすべて遺言執行者が行うことになります(下記「遺言執行者の業務」参照)。この場合、相続人は、遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
例えば、以下のような場合に遺言執行者を決めておくと、手続きがスムーズに進みます。
遺言執行者を指定する方法
遺言執行者は、遺言で指定することができます。
具体的には、遺言書に
「本遺言の遺言執行者として、長男A(住所:大阪府大阪市…)を指定する。」
などと記載すれば問題ありません。
記載の方法があいまいだと、金融機関などで手続きが進められない可能性があります。誰を選んでいるか明確にわかるよう、氏名・続柄・住所などで特定しましょう。また、選ばれた人が驚いてしまわないよう、事前に遺言執行者になってほしい旨を伝えておくことをおすすめします。
このように直接指定するほか、自分が亡くなったときに遺言執行者を指定する人を指定することもできます。例えば、「残された妻が信頼できる人物を自分で選んでほしい」といった場合に、この方法が使えます。
なお、遺言者の死後、遺言に指定がない場合や、指定された人が拒否した場合、業務ができない場合などには、家庭裁判所に遺言執行者を指定してもらうよう申し立てることもできます。申立ての際には、事前に候補者を選んでおくことも可能です。ただし、最終的には家庭裁判所の判断で選ばれることになるので、親族を候補者にしていても、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。
遺言執行者の業務
では、このようにして選ばれた遺言執行者は、具体的にどのような業務をするのでしょうか?
遺言執行者が業務を始めるタイミングは、以下のとおりです。
- 遺言で指定された人:遺言者が亡くなり、かつ、遺言執行者になることを承諾したとき
- 家庭裁判所が指定した人:家庭裁判所の決定が下りたとき
そして就任後は、以下のような順で相続手続き(遺言の執行)を進めていきます。
ステップ1:相続人を調べ、相続人全員に就任通知書を送る
業務を開始した遺言執行者は、事情の許す限りできるだけ速やかに、「自分が遺言執行者に就任したこと」および「遺言の内容」を、相続人全員に通知しなければなりません。
そのためにも、まずは亡くなった遺言者(被相続人)の戸籍を調べて、相続人を確定させる必要があります。
通知書は、以下のような様式で作ります。
遺言執行者就任通知書
遺言者
氏名:B(令和○年○月○日死亡)
本籍:……
最後の住所:…
拝啓
この度、上記遺言者の遺言公正証書(大阪法務局所属公証人○○作成令和○年第○号)において、私が遺言執行者として指定され、就任を承諾いたしましたので、ご連絡いたします。
これに伴い、遺言者Aの相続財産の管理及び遺言執行に必要な一切の権限は遺言執行者である私に属することとなります。なお、相続財産につきましては、調査完了後に改めてご報告させていただきます。
ご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせくださいませ。何卒、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
敬具
遺言者B相続人各位
令和○年○月○日
遺言執行者A
住所:…
電話番号:…
通知の際には「遺言者は誰か」「いつ亡くなったか」「遺言執行者の連絡先」を明確にしましょう。また、後から受け取っていないと言われてしまう事態を避けるため、内容証明郵便で送ることが望ましいです。ただし、内容証明郵便だと精神的に圧力を感じてしまう方もいらっしゃるので、相手によって適宜通知の方法を選ぶことも重要です。
ここで、相続人全員に通知書を送るという点に疑問を感じられる方もいらっしゃるでしょう。「会ったことがない相続人がいる」「財産を受け取れない相続人に連絡するのは気が引ける」といった理由から、通知書を送りたくない場合もあるかもしれません。
しかし、遺言執行者には全員に通知を送る法律上の義務があります。
その理由として、相続人には遺留分を請求する権利や、遺言書の有効性に異議を唱える権利があります。これらの権利を守るため、遺言執行者は、① 相続が発生したことと② 遺言の内容を知らせる必要があるのです。
財産を分配してしまってから争いにならないよう、全員に通知するようにしてください。
ステップ2:相続財産を調べ、財産目録を作成する
次に、被相続人の財産や負債を調査し、財産目録(財産と負債の一覧表)を作成します。
遺言者が遺言に財産目録を残していれば比較的容易に調査できますが、手掛かりがない場合、次のような財産をくまなく探さなければなりません。
- 財産
:不動産/銀行預金(普通預金・定期預金)/株式/投資信託/医療保険/年金/事業用資産など - 負債
:金融機関からの借入れ/消費者金融からの借入れ/住宅ローン(団体信用保険により完済されることも)など
こういった財産を調べるには、自宅にある不動産の権利書や通帳、保険証券などを確認するほか、各機関から次のような資料を取り寄せます。
- 不動産
:登記事項証明書(法務局)、固定資産税評価証明書(役所)、名寄帳(役所) - 銀行預金・株式・投資信託
:残高証明書(銀行や証券会社) - 各種借入れ
:残高証明書(借入先)
財産に漏れがあったり、相続人同士で財産の価値の認識に違いがあったりすると、後で争いになりかねないので、できる限り客観的な資料で確認するようにしましょう。
調査が終われば、財産目録を作成して各相続人に通知します(調査が素早く終わりそうであれば、前述の就任通知書と一緒に送ってもよいでしょう)。
ステップ3:相続手続きを進める(遺言の内容を執行する)
続いて、遺言の内容に従って実際に財産を分配します。
具体的には、預貯金・株式等の金融資産の解約や名義変更、不動産の名義変更(相続登記)などを行いますが、これらの手続きには通常、財産を受け取る人(相続人や受遺者)の協力が必要です。
また、財産の分配以外にも、遺言に「相続人の廃除」や「認知」に関する事項が書かれている場合は、遺言執行者が手続きを行うことになります。
そのほか、例えば遺品整理や相続税の申告など、相続人がすべきことであっても、遺言執行者がサポートできることもあるので、協力して進めるようにしましょう。
ステップ4:相続人に業務の完了を報告する
遺言の内容をすべて実行できたら、相続人に業務の完了を報告します。
報告の形式は、最初に送った就任通知のような手紙を送ればOKです。
この報告をしなければ、法律上、遺言執行者としての業務が終わったことになりません。必ず報告するようにしましょう。
遺言執行者の権限
ここまで遺言執行者の役割や指定の方法、業務の流れを確認しましたが、これからはより法律的な観点から遺言執行者の権限を解説していきます。
遺言執行者は「遺言に書かれた内容を実現すること」ができますが、その具体的な権限は法律で定められています。その権限外の行為をすると、あとから無効になったり、相続人の権利を害してしまったりして、トラブルの火種になりかねません。
法律で定められた遺言執行者の権限は、次のとおりです(ただし、平成30年(2018年)7月の民法改正後)。特に独占とあるものは、遺言執行者にしかできない法律行為であり、たとえ相続人であっても、遺言執行者以外の人はすることができません。
このような強い権限がある一方で、「遺言に書かれていない財産」や「相続人間で話し合って決めるよう遺言で指示されている事項」については、遺言執行者には何の権限もありません。このような部分については、相続人が手続きをしなければならないので、注意が必要です。
特定財産承継遺言とは、「特定の財産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言です。
具体的には、「長男Aに、私が所有する不動産(所在:大阪市…、地番:…、家屋番号:…)を相続させる」や「妻Bに、すべての財産を相続させる」といった内容が書かれた遺言を指します。
相続登記や預貯金の解約などの行為を遺言執行者が単独でするには、このような特定財産承継遺言により、手続きの対象となる財産とその財産の帰属先がはっきりと特定されている必要があります。「長男Aと二男Cに、私が所有する財産を2分の1ずつ相続させる」といった書き方では、個々の財産がAとCどちらに帰属するのかわかりません。このような内容では遺言執行者の権限外になってしまうので、注意しましょう。
誰を選任する? 選ぶときの注意点
法律上、未成年と破産者以外であれば誰でも遺言執行者になることができます。財産を受け取る相続人でも構いませんし、相続の専門家でも構いません。
実際には、以下のような人が遺言執行者になることが多いです。
- 配偶者や子どもなどの信頼できる家族
→ 指定された人が相続発生時に遺言執行者になれない場合を想定して、二番目の候補者を指定しておくと安心です。 - 弁護士や司法書士、税理士などの専門職
- 銀行などの金融機関
家族に依頼すると、費用がかからないというメリットはありますが、平日にしかできない手続きや専門知識が必要となる手続きも多く、負担となってしまうこともあります。
専門職や金融機関に依頼すれば、一定の費用はかかりますが、安全かつ確実に相続手続きを進めることができます。
特に財産の内容が複雑であったり、相続人間の対立が予想されるような場合には、中立な立場で手続きが進められる専門職等を遺言執行者に指定することをおすすめします。
※ 家族を遺言執行者にした場合であっても、その遺言執行者から専門家に手続きを代行するよう依頼することもできます。
遺言執行者の義務・報酬
遺言執行者の義務
ここまでは遺言執行者は「何ができるか」を中心に解説しましたが、最後に、「何をしなければならないのか」という遺言執行者の義務を確認しましょう。
遺言執行者には、これまで紹介した義務も含め、次のような義務があります。
遺言執行者がこのような義務に違反すると、相続人が不利益を被りかねません。そのような事態を防ぐためにも、信頼できる誠実な人や、仕事として遺言執行をしている専門家を遺言執行者に指定してください。
正当な理由があれば、解任や辞任をすることも可能
遺言執行者が上記のような義務に違反した場合、相続人やその他の利害関係者(受遺者や債権者)は、相続人を解任するよう家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言執行者側も、病気や長期出張などの理由があれば、家庭裁判所に辞任を申し出ることが可能です。
ただし、解任・辞任どちらの場合にも「正当な事由」が必要です。「気が合わないから解任したい」「面倒だから辞任したい」といった理由では受け付けられませんので、注意してください。
遺言執行者の報酬
そして気になる遺言執行者の報酬ですが、家族を指定する場合は、報酬を与えても与えなくても構いません。与える場合には、遺言書にその旨を記載してください。ただし、この報酬は通常、受け取った遺言執行者の雑所得となります。
また、弁護士や司法書士、税理士といった専門職や金融機関を遺言執行者とする場合、それぞれが定めた報酬が必要となります。具体的な費用は依頼先に確認する必要がありますが、相場としては相続財産の1~3%程度(最低報酬額が決められている場合や、手続きの煩雑さにより加算される場合もあり)が目安です。
この報酬は、原則として相続財産から支払われます。その他の経費も含め、相続人が個人の財産から支払わなくて済むよう、相続発生時にかかる費用を事前に想定しておきましょう。
まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために重要な存在です。相続手続きはどうしても複雑になりがちですが、遺言執行者を代表者に指定しておくことで、相続人の負担が軽減でき、手続きをスムーズに進めることができます。
ただし、その業務の内容や権利・義務は、法律で細かく決められており、専門的な知識を要する場面もあります。また、役所や銀行の手続きなど、平日に時間を割いて動かなければならない場面もたくさんあり、負担に感じられることもあるでしょう。そのため、相続人間でトラブルが起こりそうな場合や、遺産の内容が複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者を決めるべきか、どのような人を選ぶべきか、疑問のある方は、遺言を書く前にぜひお気軽にお問い合わせください。

執筆・監修:司法書士 廣畑 優(ひろはた司法書士事務所代表)
大阪市に事務所を構える司法書士/相続・遺言・家族信託・成年後見など、家族や財産に関する手続きを中心に幅広く対応
1級ファイナンシャル・プランナー(FP)資格も保有し、法務とお金の両面からご家庭をサポート/「わかりやすく、誠実に」をモットーに、安心して相談できる身近な専門家を目指しています。